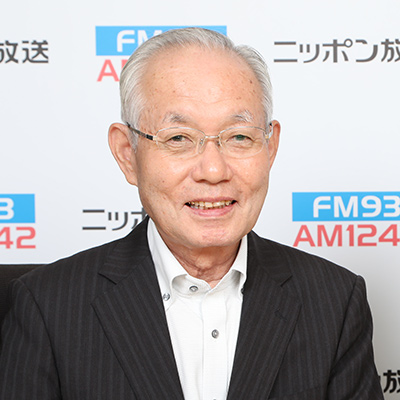第32回のテーマは「日本人のインフラ観と道路のネットワーク評価」
番組アシスタントの新保友映です!
今回は、「日本の道路整備において欠けている重要な視点『リダンダンシー(冗長化)』」について、大石さんが詳しくお話します。
新保 日本の道路が整備されたのは、いつ頃からでしょうか?
「社会を支える基礎構造である都市城壁(=インフラ)を必要としなかったわれわれ日本人は、インフラに関心を払ってきませんでした。特に日本の道路は、戦前まではほとんど整備されておらず、舗装もされていなかったし、大型車がちょっと山道に行くとすれ違いが出来ない、そんな道路ばかりでした。昭和20年代の終わりに、政治家や官僚がやがて日本にもモータリゼーション(自動車化)の時代が来るからその準備をしようと、考え始めました」(大石)
新保 その道路整備が始まったのは?
「昭和30年ごろ、東京と大阪の間を高速道路で結ぼうという構想が持ち上がりました。昭和31年に世界銀行からお金を借りて高速道路を造ることになり、その調査団の団長・ワトキンスの調査報告書には、『日本の道路は信じがたいほど悪い、工業国にしてこれほど完全にその道路網を無視してきた国は日本の他にない』と書かれていました」(大石)
新保 それほど日本の道路事情は悪かったんですね。当時の写真を見ると、雨でぬかるんだ道にタイアがはまり、みんなで車を押していますね。
「これは田舎道ではなく、いまでいうと国道一号というような幹線道路です。これでは経済を支えることはできません。さらに晴れているときは砂埃が上がって、周辺住民からの苦情も出ていたようです。そこでまずは舗装をしようというのが、道路整備の始まりでした」(大石)
新保 工業国でこれほど遅れた国は他になかったんですか?
「ドイツには、ベルリンとその他の都市を結んでいる道路が途切れても、他の道路でつながる代替路線があります。ドイツ人にはそのようなネットワークづくりの考えが基本にあります。そうなった理由は空襲でした。空から爆弾が飛んできて、ベルリンとの輸送が途切れてしまったら成り立たない、途切れても代替路線で繋がるようにするというのが、ドイツ人の考え方です」(大石)
新保 日本でも「代替路線」が求められているんですね。
「これを国土交通省では『リダンダンシー(冗長化=余分に付加されることで、より機能の安定化が図られること)』という言葉で表しています。代替路線の必要性を、私たちは阪神淡路大震災で経験しています。幹線道路・幹線鉄道が全部止まり、東西が完全に途切れてしまいました。結果、日本海側に車が集中して大渋滞になりました。こういうことが起きないようにドイツでは初めから道路ネットワーク整備の考え方の中に、リダンダンシーが入っています」(大石)
新保 東日本大震災の時も物流がストップしてしまいましたね。
「東日本大震災が起きたとき、(太平洋沿岸沿いを走る)国道45号がズタズタにやられました。山側を通る三陸自動車道は、やや高いところを橋とトンネルを多用しながら造られています。しかし交通量が少ないこともあって、整備が遅れていました。当時の三陸自動車道は、最初の区間の開通から30年が経つのにまだ半分しか出来ていませんでした。これではいけないと、超党派の議員さんたちが動いて、間もなく結ばれようとしています」(大石)
新保 東京と青森は何通りの道で結ばれているんですか?
「東京から青森までバックせずに何通りの道があるのかを調べたら、2011年の時点では42通り。2019年3月には256通りに増え、あと8%の道路を延ばすことで、1万4200通りに増えることがわかりました。たった8%ですが、そこをつなぐことによってネットワークの柔軟性が飛躍的に上がります。災害大国の日本として追求すべき価値だと思います」(大石)
今回は、災害大国の日本だからこそ、交通量が少なくても道路を整備していく大切さがよく分かるお話でした。詳しくは、上記の「聴き逃しサービス」をクリックして、ぜひ、番組をお聞きください!
*大石久和のすっきり納得!経済教室*
今回は『銀行がお金を貸すということは、どういうことなのか』というお話です。例えば、事業を始めるとき、その資金を銀行から借りるとします。銀行は借主を信用してお金を貸し出します。そのお金は、銀行の預金者のお金をかき集めているわけではなく、必要な金額を通帳に書き込むだけのことです。書き込むだけのお金なので『万年筆マネー』とも言われています。これは銀行の特別な機能で、銀行が貸し出すということは、貨幣を創造していると言ってもいいのです。
これは国債の購入でも同じです。例えば、政府が発行した国債が200億円分とします。それを引き受ける銀行は200億円を用意するわけではありません。日銀に預けている銀行の当座預金が、政府の当座預金に切り替わるだけで、キャッシュが動くことはありません。政府の財政赤字、つまり政府の債務というのは、それと同額の新たな民間貯金を生むと言ってもいいのです。
「政府に返済能力はあるのか?」と疑問を持つ人がいますが、政府は日銀を従えており、その日銀はお金を印刷することができるので、政府の返済能力ははっきり言って無限大です。したがって政府の返済能力を気にする必要はありません。
我々はこれまであまりにも財政拡大をやってこなかったために、経済成長せず、ありとあらゆるところに歪みが出ています。世界の中の劣後国と言ってもいいような状況が生まれているのは、ここの理解が間違っていたから、と言ってもいいと思います。
-

2021.03.22
第65回のテーマは「驚きが始まりだ」と「われわれは何処に立っているのか」
番組アシスタントの新保友映です! 突然のお知らせですが、2019年10月6日からお送りして来ました「ラジオ国土学入門」。実は今回が最後の授業となりました。第65回目の講...
-

2021.03.15
第64回のテーマは「経済成長とインフラ」
番組アシスタントの新保友映です! きょうは「経済成長とインフラ」についてのお話です。 新保 これは、大石さんのいつも主張されてきたテーマですね! 「『経済成長』と『...
-

2021.03.08
第63回のテーマは「価値観を共有できない日本人」
番組アシスタントの新保友映です! きょうは「価値観を共有できない日本人」についてのお話です。 新保 日本は世界から遅れているという話が多いのですが、価値観も? 「近...
-

2021.03.01
第62回のテーマは「電力崩壊の危機」
番組アシスタントの新保友映です! きょうは「電力崩壊の危機」についてのお話です。 新保 大陽光発電などの普及で、日本の電力は余っているのでは? 「いえ、今の日本は、...
-

2021.02.22
第61回のテーマは「リアリズムを失ってしまう日本人」
番組アシスタントの新保友映です! いよいよ2月24日に大石さんの新刊『「国土学」が解き明かす日本の再興 ― 紛争死史観と災害死史観の視点から』(海竜社)が発売されます。...