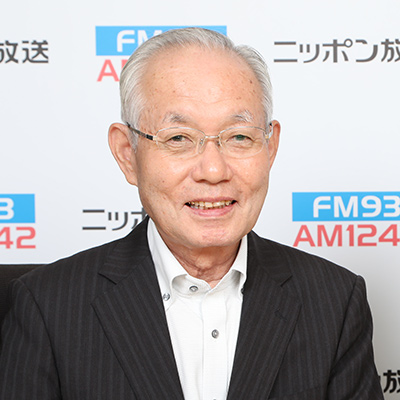第28回のテーマは「自然災害死史観と紛争死史観」
番組アシスタントの新保友映です!
いま世界は新型コロナウイルスによって、多くの方が感染し、尊い命を亡くしていますが、今回は大石さんが〝死〟について、日本とヨーロッパの違いについてお話します。
新保 歴史を振り返ると、戦争があったり、災害があったり、様々な〝死〟がありますが、日本人とヨーロッパ人では、その受け入れ方に違いがあるそうですね。
「日本で多くの犠牲者が出るのは、大地震、大洪水、大津波、大高潮など、自然災害によるものです。一方、ヨーロッパや中国では、自然災害よりもはるかに多くの人々が紛争(戦争)で亡くなっています。自然災害で家族(愛する者)の命が奪われたとき、恨むべき相手はどこにも存在しません。従って自然災害による日本人の死は、非常に悲しくて苦しい死です。これに対し、ヨーロッパや中国では、敵に家族(愛する者)の命を奪われたという死なので、そこには殺した相手が必ず存在します。ですから、相手を恨んで恨んで恨み抜き、やがて復讐の誓いを立てることによって、その死を受け入れてきたというわけです。われわれ日本人とユーラシア人の考え方(思考の組み立て方)の違いは、こうした民族の経験の違いに由来しています。
新保 恨む相手が、自然か、外敵かで考え方が違ってくるわけですね。
「ヨーロッパや中国では、敵から攻めてこられないように都市を城壁で囲みました。日本はそういう必要がありませんでした。城壁で囲んだ国と、囲まなかった(囲む必要の無かった)国とでは、物事の考え方が違ってくるのです。その考え方の違いは今もわれわれの生活に残っていて、日本の家のドアは外開き、ヨーロッパのドアは内開きです。内開きのドアの方が内側から押し返して防御しやすいのです。このように日本では『自然災害死史観』が、ヨーロッパ・中国では『紛争死史観』が生まれました」(大石)
新保 さらに大石さんが調べたことが、紛争による死者数だったそうですね。
「紛争でどのぐらいの人間が死んだのか、ということを調べてみると、日本の場合、関ヶ原の戦い、川中島の戦いの死者数を調べてもはっきりした数字が出てきません。死者数に注目する歴史家がいません。世界ではどうかというと、アメリカ人の歴史研究家、マシュー・ホワイト氏が、『殺戮の世界史 人類が犯した100の大罪』(早川書房)という画期的な本を出しています。この本では、人類が行った世界中の殺戮行為と、その死者数が調べ上げられています(ヨーロッパ人・中国人が、如何に「紛争による大量虐殺・殲滅戦」を経験してきたかが示されています)。
この本は、日本ではまったく注目されなかったのですが、それは日本人が殺戮に関心がないからだと思います。たとえば、大虐殺を表す英語は、ジェノサイド(genocide)、ホロコースト(holocaust)、ホミサイド(homicide)、カーネイジ(carnage)、スローター(slaughter)、マサカー(massacre)、ブッチャー(butcher)、エクスターミネイト(exterminate)など、他にもいくつもあり、それぞれ虐殺の意味が違います。日本語では、殺人、殺戮、虐殺の三つぐらいしかありません」(大石)
新保 こういう虐殺の歴史も国土学に含まれるんですね…。
「あのフランス革命では150万人の犠牲者が出ています。自由・平等・博愛を目指したフランス人が150万人もの人々を殺しています。当時はギロチンで処刑し、その日は屋台が出てお祭り騒ぎだったそうです。これほどまでの犠牲を出し、いかなる殺戮を犯してでも、彼らは求めなければならない正義があると考えています」(大石)
新保 そのあたりの正義は、なかなか日本人には理解できないところですね…。
「人類皆兄弟…、同じ人間だから話し合えば分かるという世界ばかりではなく、日本人には理解できない世界もあります。紛争死を経験してきたヨーロッパ人は、次の戦いで勝利するための方法や準備を極めて合理的に思考してきました。一方、自然災害死を経験してきた日本人は、自然災害が起こってからしか物事を考えることができない…。こうして、ヨーロッパ人は『合理思考』の民族になり、日本人は『情緒思考』の民族になったのだと思います」(大石)
新保 今回は、ちょっと怖い話になりました。そういう歴史や国土の違いが、ヨーロッパや中国にあって、日本との違いを生み出していることも理解すべきではないでしょうか。詳しくは、上記の「聴き逃しサービス」をクリックして、ぜひ、番組をお聞きください!
-

2021.03.22
第65回のテーマは「驚きが始まりだ」と「われわれは何処に立っているのか」
番組アシスタントの新保友映です! 突然のお知らせですが、2019年10月6日からお送りして来ました「ラジオ国土学入門」。実は今回が最後の授業となりました。第65回目の講...
-

2021.03.15
第64回のテーマは「経済成長とインフラ」
番組アシスタントの新保友映です! きょうは「経済成長とインフラ」についてのお話です。 新保 これは、大石さんのいつも主張されてきたテーマですね! 「『経済成長』と『...
-

2021.03.08
第63回のテーマは「価値観を共有できない日本人」
番組アシスタントの新保友映です! きょうは「価値観を共有できない日本人」についてのお話です。 新保 日本は世界から遅れているという話が多いのですが、価値観も? 「近...
-

2021.03.01
第62回のテーマは「電力崩壊の危機」
番組アシスタントの新保友映です! きょうは「電力崩壊の危機」についてのお話です。 新保 大陽光発電などの普及で、日本の電力は余っているのでは? 「いえ、今の日本は、...
-

2021.02.22
第61回のテーマは「リアリズムを失ってしまう日本人」
番組アシスタントの新保友映です! いよいよ2月24日に大石さんの新刊『「国土学」が解き明かす日本の再興 ― 紛争死史観と災害死史観の視点から』(海竜社)が発売されます。...