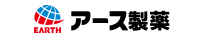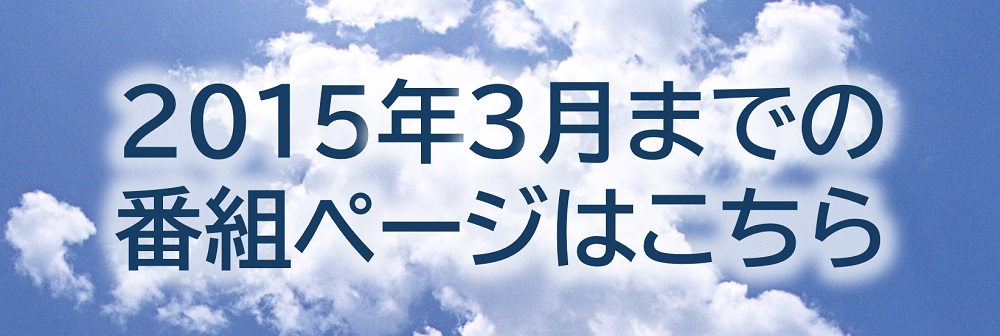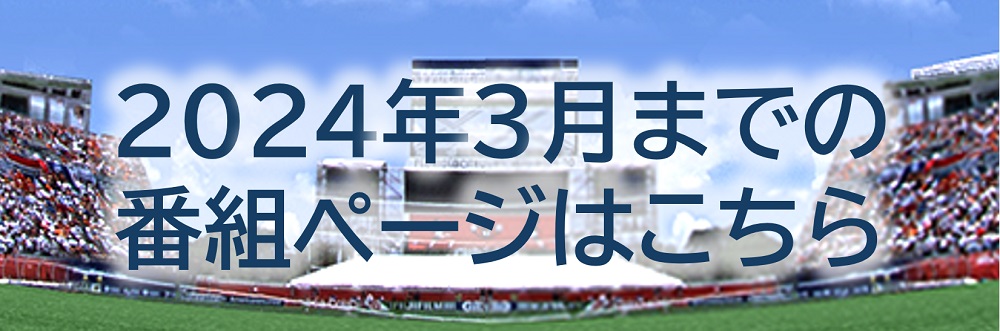倉野直紀(全日本ろうあ連盟本部事務所長・デフリンピック運営委員会事務局長)
今年の11月15日から26日までの12日間、東京都を中心に開催される「東京2025デフリンピック」。「デフリンピック」とは、英語で「耳がきこえない」という意味の「デフ」と「オリンピック」を合わせたもので、きこえない・きこえにくいデフアスリートによる国際スポーツ大会です。1924年、フランスのパリで第1回大会が行われ、東京で行われる今大会は、100周年の記念大会。
今週は「東京2025デフリンピック」について、運営を担当されている全日本ろうあ連盟本部事務所長で、デフリンピック運営委員会事務局長の倉野直紀さんにお話を伺います。なお、倉野さんは耳がきこえないため、手話通訳・梅澤仁士さんを介したインタビューになります。
▪︎倉野さんがデフスポーツと関わるようになったきっかけは?
「私15年前から日本、全日本ろうあ連盟の理事になりました。そのときに、全日本ろうあ連盟スポーツ委員会の事務局長というものを拝命しました。それまでデフリンピックもデフスポーツも全く知らないというような状態でした」
「ですけれども、事務局長になったことがきっかけで、2017年にトルコで開催されました夏季デフリンピックの日本選手団の総務として参加をすることになりまして。それ以降3大会で日本選手団の総務として、選手団として参加をしており、そこからの関わりがあります」
▪︎実は、パラリンピックに、デフスポーツは含まれていない。
「実はデフリンピックとパラリンピック、合同でやろうかというような話もあったことはあったんですね。今から30年ほど前のことです。なんですけれど、色々な課題が出てきてしまいました」
「1つ目は、まずデフリンピックの場合、本当に耳が聞こえない以外は、記録を争う場というところです。なので、オリンピックと同じということになります。というのは、30年前のパラリンピックといえば、まだまだリハビリというような考え方が残っていたということ。それと、もしデフリンピックをパラリンピックと一緒にやった場合、競技の数が40近くになるんですね。オリンピックよりも大きな大会になってしまうんです。なので、合同にはしないで、それぞれの独立した大会をする、お互いにそれを尊重し合って進めるということになりました」
▪︎デフリンピックが東京で開催される意義は?
「東京オリンピック・パラリンピック、そのレガシーですね。これを引き継いで、さらに発展をさせていきたいという風に思っています。特に、聞こえない私たち、今残されているバリアー、やっぱりコミュニケーションのバリアがまだ残っているんですね。音声での情報、それが閉ざされているバリアー。それを取り払う。そういったことを進めていきたいと思っています」
▪︎2022年9月、オーストリアのウィーンで行われた国際ろう者スポーツ委員会総会で、東京開催は満票で決まった。
「やっぱり各国と話してみてわかるのは、期待3つほどあります。1つ目がやはり日本という国ですね。日本の文化。また、日本は アスリートとして素晴らしい競技施設がたくさんある。デフアスリートにとっても非常に嬉しいことだということがあると思います」
「3つ目が、日本で100年かけて初めて開催をするということ。素晴らしい大会を見せてもらえるだろう、という期待をされているという部分があるんですね」
「準備についても、東京都と一緒に準備を進める、それにあたって非常にいい雰囲気で、いい関係づくりをしながら進めていけてると感じています。聞こえる人たちが一緒にやるという、運営するという形は、この東京大会が初めてになります。これも、今回幸い、東京都の皆様もご理解をいただいて、一緒に業務を進めることができている。これはいい大会にできるな、という風に思っています」
▪︎東京デフリンピックには、70から80の国や地域から、選手・審判員・スタッフ合わせておよそ6000人が参加する見込みだ。
「デフリンピックの特徴が2つありまして、1つ目が、大会の中で、選手・スタッフのコミュニケーションというのが国際手話というものを使います。2つ目が、選手また市民との交流、そういった場を作る。『デフリンピックスクエア』というものを設ける予定になっています。それが特徴です」
「国際手話については、大会で必要になる国際手話の人数……国際手話ができる人の育成に今取り組んでいるところです」
▪︎東京デフリンピックを“きこえる人”が生で観戦する際に、気をつけてほしいことは?
「まずはですね、デフアスリートは聞こえないので、音声で応援するということは伝わらないです。ですので、過去のデフリンピックの大会でも見てますと、応援の仕方はですね、例えばタオルを振り回したりとか。応援の言葉『がんばれ』とか『いけ!』とか、そういった書かれたボードを掲げている」
「また、他にですね、体を使ってジェスチャーで応援をするのを、各国でやったのを見ています。日本でもぜひ、市民の皆様が見ていただくときは、目で見て分かる応援をしていただけるとありがたいですね」
「拍手はですね、聞こえる人の場合は手を叩く動作をしますけれども、私共聞こえない者はその代わりに、手をちょっと上の方に向けて、両手を上に開けて、ヒラヒラと動かす動作をします。これが世界共通の拍手。聞こえない人の拍手になります」
▪︎東京デフリンピックをきっかけに、スターになりそうな選手はいるのだろうか?
「私が思う今のスターは、水泳の茨(隆太郎)選手。茨選手は、中学生の時からデフリンピックに出場し続けています。東京2025のデフリンピックももし参加するということになると、5大会連続出場ということになるんですね。『日本のデフリンピックマン』と言ってもおかしくないなと思います」
▪︎倉野さんが思う、デフスポーツの魅力とは?
「スポーツをやる上で、音っていうのが非常に重要だと思うんです。例えば卓球、バドミントン。そういった競技については、打球音というのが思ったより大切なんですね。それがですね、デフアスリートの場合はそれが全く聞こえませんので、その代わりにその打つところを目で見る、目で追うという戦いになります」
「サッカーも同様だと思います。サッカーの場合は、後ろは見てませんので、声はもちろん聞こえません。その場合ですと、お互いがアイコンタクトをする。または走りながらサインを出す。サインを出しながらプレーをするということですね」
「聞こえる人の戦い方と、デフアスリート、デフサッカーの戦い方っていうのは違いがあるんですね。そういったところをぜひ注目して。そこがデフスポーツの魅力だという風に思っています」
-

2026.01.19
槙原淳幹(身体障がい者野球・日本代表主将)
1989年生まれ、岡山県出身の36歳。生後10カ月のときに事故で右腕が動かなくなり、左手で生活しています。小学3年生から左手だけで野球を始めると、高校時代には軟式野...
-

2026.01.12
大日方邦子(ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会 日本代表選手団団長)
1972年生まれ、東京都出身の53歳。3歳のときに事故で右足を切断、左足にも障がいが残りました。高校2年生でチェアスキーと出会い、日本代表として活躍。冬季パラリンピッ...
-

2026.01.06
増田明美(日本パラ陸上競技連盟会長)
1964年生まれ、千葉県出身の61歳。現役時代は陸上の長距離選手として活躍。1984年、初めて女子マラソンが採用されたロス・オリンピックに出場しました。1992年...
-

2025.12.22
吉田彩乃(パラ陸上・車いす)
2006年生まれ、横浜市出身の18歳。先天性の脳原性まひのため両脚に障がいがあり、車いすで生活しています。中学2年生から本格的に車いす陸上を始め、2023年、高校2年...
-

2025.12.15
森井大輝(パラアルペンスキー・座位)/村岡桃佳(パラアルペンスキー・座位)
●森井大輝選手 1980年生まれ、東京都あきる野市出身の45歳。トヨタ自動車所属。4歳からスキーを始めますが、16歳のときに事故で脊椎を損傷。その後、座って滑るチェ...