第146回『エース登板』
誰も人が居ない夕暮れの有楽町LFの駐車場。
ラジオの生放送を終え 日比谷で映画を観て駐車場へもどると 駐車場の一番奥で自転車と格闘する男。
私はTVで見て知っているから「あれは大好物のバッテリィズのエースだな」と思ったので声をかけた。
「どうした?自転車こわれたのか」「そうなんすよ。どうしよう」
私はTVで見てるから知っているので「なに?この自転車で局への移動しているの?」「そうなんすよ。まだ東京のことも分からなくて」
エースはまったく私のことなど知らない。
当然だ。東京へ出てきたばかりだし……
キャリアもまったく違うし
「これから何処へ行くんだ?」「えーと ニッニッニッテレ?」
「麹町の?」「そうなんすかねぇ」「オレ近いから送ってってやるよ」
「そうすか。すいません(と気がついて)自転車と乗れるか!!」
「アハハそうなの?オレ トラックだよ」「トットットットラック~~~?」
こんな行きずりのトークがあって 色々あって 相方の耳にはあの相手は私だと知らされたらしいが
エースには何が何やら分からない。
ラジオで相方が「その声かけて来た人はどんな人だったんや」「えーと……気さくなダンディ」だって。
ギャハハ 東京人をこれ程短い言葉で表現した人は今まで居なかった。
さんぽ会で集まった連中からも
「たったふた言。オレ達が何十年もつきあっても表現できなかったセンセーを“気さくなダンディ”とは。おみごと」の声が沢山。
嬉しい。私はズ――ッと気さくすぎるのだ。偉人感が欲しい。
紫綬褒章はいらないから とっつきにくさが欲しい。

ついに五刷。ラジオでの私のひと言から始まった「爆弾犯の娘」のミニ・プチブーム。
五刷で書店に並ぶ分からは とうとう帯に私まで登場しちゃっている。
感涙!泣いちゃいないけどね。
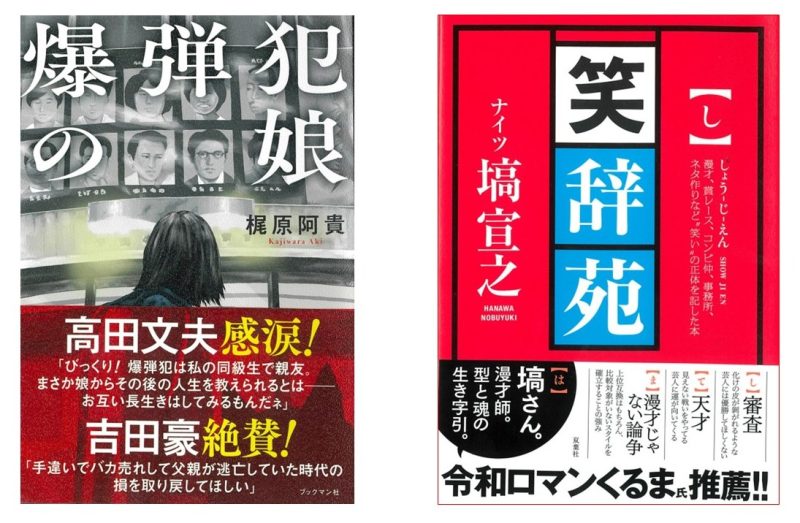 漫才協会会長であり土屋の知り合いでもあるナイツの塙が出した「笑辞苑」。
漫才協会会長であり土屋の知り合いでもあるナイツの塙が出した「笑辞苑」。
「笑い」に関する考察だらけの名文と駄文のオンパレード。ここ5年間くらいの芸人の歴史も内側から分かる。
作家には書けない現場のリアルな声。
下のイラストは一之輔が「週刊文春」で隔週で書いている日記。
金沢へ太田光らと行った「オール日芸寄席」のことを書いている。
次の日 一之輔と志ららを連れて金沢ウロウロ。
まさにまるで水戸黄門御一行。
「どこが悪いの?」ときかれて「目と肛門」(そんなこたぁ言わない)
塙だったら「肛門見えても」だ。
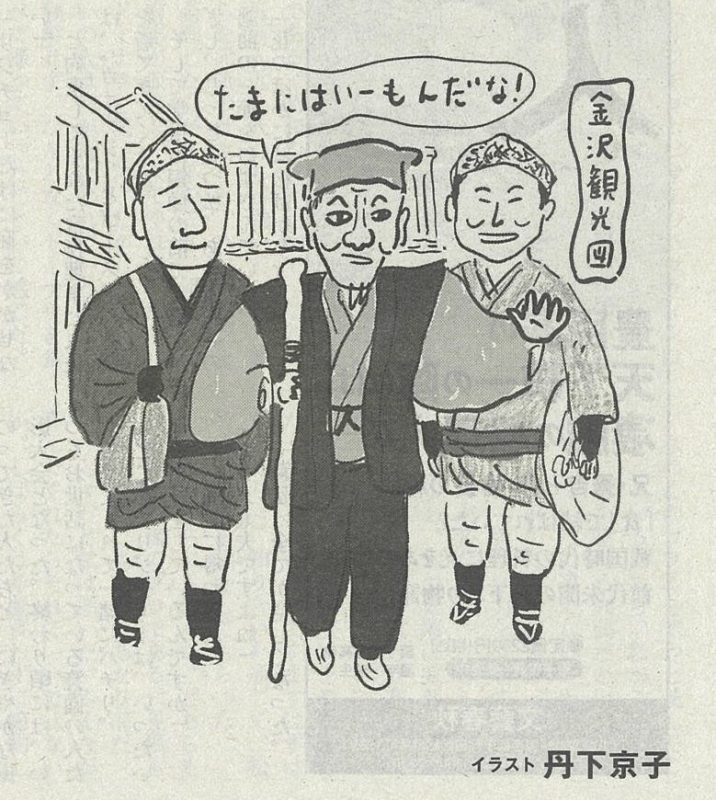
たい平 手作りの「ガンバレ!ペーパー(紙)新聞」 2回開催された応援の会で配られたもの。
中の左に文枝師のコメント その下に私のコメントが載っている。
当日は岩崎宏美、戸田恵子らも駆けつけた。なんと岩崎宏美は2曲歌った。
先日バッタリ会った戸田恵子「仕事の合い間ぬって私も駆けつけたわよ。ペーパー新聞まで すみずみ読んだけどさ。手ぬかずに あんな小さい所まで書いてたじゃない。読んでますからネ!」と言ってアンパンマンは去っていった。
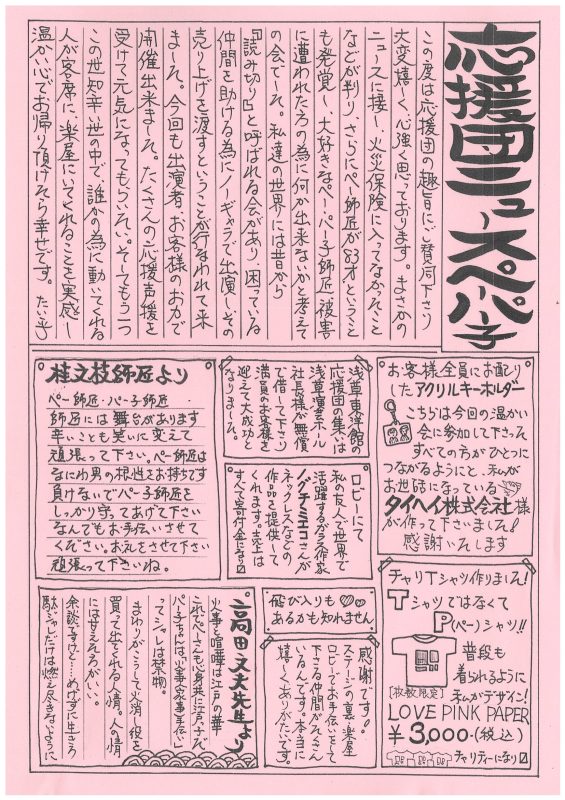
別の日は私は東洋館で「ホームラン勘太郎」を偲ぶ会。たにし主催。
こちらでは鳥羽一郎が靴下で2曲歌った。生「兄弟船」しびれたねぇ~。
こんな所に居たのか 快楽亭ブラック。
立川流を去ってから もう何年になるのか。
その間 私は一度だけ試写室で見かけたことがある。
そこで なんとドキュメント映画ができたらしい。
「落語家の業(ごう)」だとさ。
“コンプライアンスの超越者”とある。
12月13日(土)より渋谷ユーロスペース。
怖いものみたさで見に行く人も何人かは居ると思う。
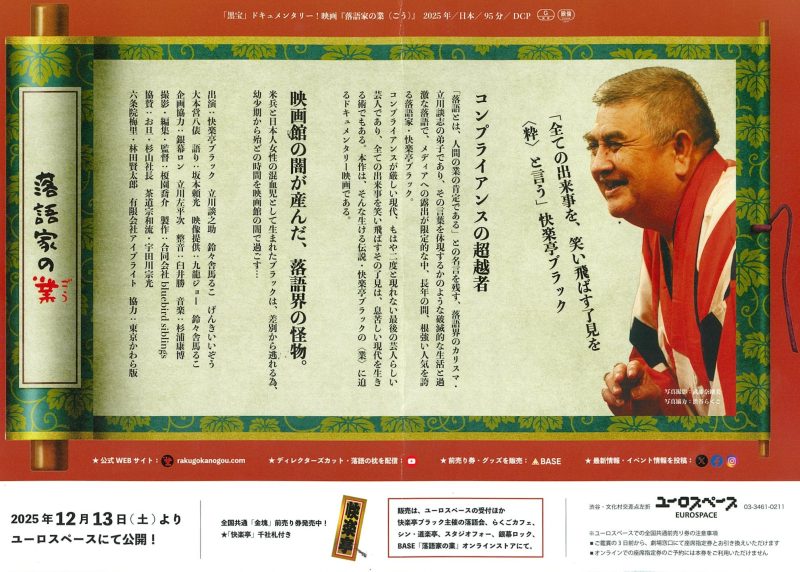
渋谷PARCO劇場へ行って「作・演出 宮藤官九郎」の「雨の傍聴席、おんなは裸足…」も観てきた。さすがは紫綬男である。
阿部サダヲは来年の「ビバデミー賞」V4を大谷並に狙っているらしい。
歌う松たか子も凄い。演歌歌手の松とミュージカル俳優の阿部の夫婦闘争である。
 皆川猿時の野郎、ちょっとしたVTR出演なのにドッカーンとウケていた。
皆川猿時の野郎、ちょっとしたVTR出演なのにドッカーンとウケていた。
14日(金)はラジオのあと「いち・にの・さんぽ会」
今回は「べらぼう」散歩。田沼意次邸跡から日本橋、人形町やらをグルグル蔦屋重三郎気分で 松村歌麿ひきつれ5人で歩く。
ゴールは神保町。飲んでバカッ話が1番楽しい。
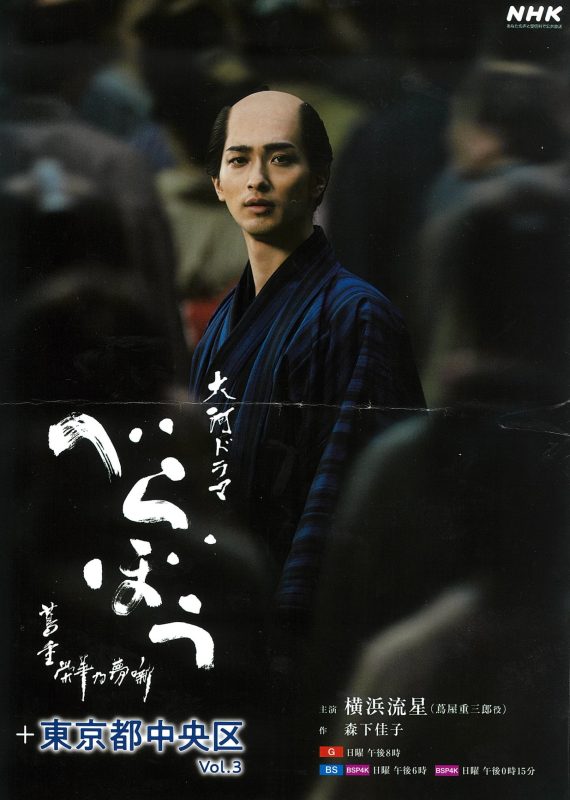
11月17日
高田文夫
-
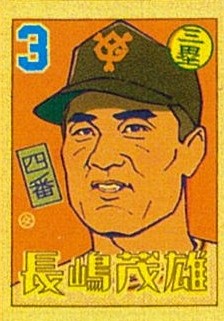
2025.12.17
第148回『ミスターフォーエバー』
さぁ年の瀬だ。 正月の準備だ。 アメ横からトー横まで行ってスジコやらカマボコやら。 年が明けると「ラジオビバリー昼ズ」には あの男たちがやってくる。 私の新年一発...
-

2025.12.04
第147回『ほんの夢の途中』
「2週間半のごぶさたでした。玉置宏でございます。ついでに笑顔でこんにちは」 という訳でもう師走だよ。77年間、女性首相じゃないが「働いて働いて―――」大していい事もなか...
-

2025.11.17
第146回『エース登板』
誰も人が居ない夕暮れの有楽町LFの駐車場。 ラジオの生放送を終え 日比谷で映画を観て駐車場へもどると 駐車場の一番奥で自転車と格闘する男。 私はTVで見て知っているか...
-

2025.11.05
第145回『グラビア磯山&ミスター寄席』
まだかまだかと待っていたら遂に「出ました達郎」。 まだか まだかの はだかの上から羽織ってますよ ちゃんと。 スタジオで喋ってる時は あまり分らないけど いざグラビア...
-

2025.10.24
第144回『ミスターFOREVER』
とうとうお別れである。 徳光さんは「ミスター寄席」をやってくれますが、本当のお別れの案内状が届いた。東京ドームである。 色んな書類も ていねいに入っていて これは行か...






