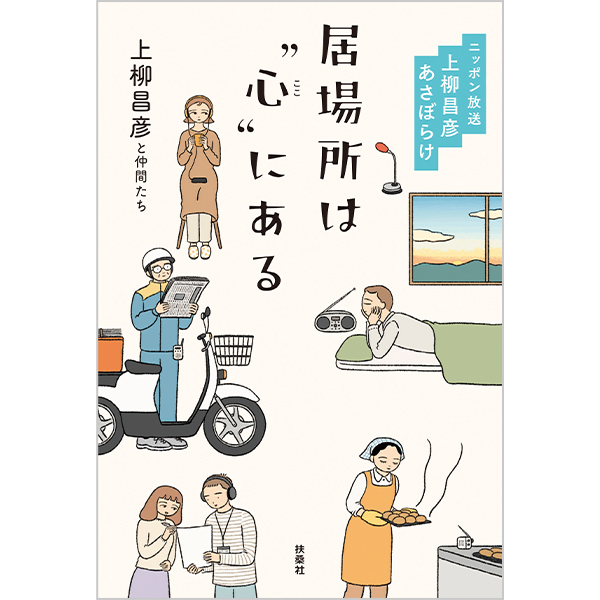「ちきゅう」
番組やこのブログでも何回か紹介した地球の内部を探査する地球深部探査船「ちきゅう」が、横浜本牧の三菱重工のドッグで5年に一度の定期点検をしていると海洋研究開発機構の方に聞き、先日三菱重工横浜製作所本牧工場を訪ねました。

数年前に清水港に停泊している「ちきゅう」の船内を取材しましたが、今回はドッグで海水を抜いた状態でスクリューや船底を見ることができました 。
この巨大な船には舵が付いていません。そのかわり直径4メートルの大きなスクリュー6つで方向を細かく変えることができます。

2011年に八戸港に停泊中に東日本大震災が発生し、大津波の前に港の海水がどんどん引いてしまい、とうとう左後方のスクリューが海底に接地してしまいその衝撃で外れてしまいました。
港内は瓦礫で埋まってしまい、海上自衛隊が海底の状態を確認している間、3日間は身動きが取れなかったそうです。
さて、この全長210m、幅38mの巨大な船はそもそも何のために10年前に建造されたのかということですが、とにかく地球の内部を調べるために、海底に長い長いパイプを降ろし、そしてそこから地面を地中深く掘るという作業をしているのです。パイプの総延長はなんと10km、重さは350tにもなります。
東日本大震災後には震源地を掘り、地中では何が起こっていたのかを調べました。またいずれは理論的には解明できても実際には誰も手にしたことがない地中のマントルを採取しようとしています。
つまりレントゲンやCTの検査である程度はわかっている地球内部を実際に解剖してみようという訳です。そうすることで地震のメカニズムや地球誕生の謎にさらに踏み込んでいこうという訳です。
甲板には船底からの高さが130mのタワー(掘削やぐら)が建っていて、マントルを採取するにはそこからパイプを次々に継ぎ足して4000mの海底へ、そして7000mの地中へと掘削をしなければなりません。

それは例えるなら14階建てのビルの屋上から直径1mmの針金を降ろして地面の直径2mmの穴に差し込むような大変な作業です。
また海底下の地中は地球が誕生したころと同じような環境で、そのような過酷な条件でも生息する原始的な生命が発見されれば、生命誕生の謎の解明にも迫れることでしょう。
しかし税収が減り借金が増え続ける日本で、「ちきゅう」を維持して、さらに多額な研究費を捻出することは容易なことではありません。
それでも地震のメカニズムを調べることで、被害を少しでも少なくしたり、生命の成り立ちを知ることで病気の予防などに役立てたりするためにも「ちきゅう」には今後とも活躍して欲しいものです。
また幼き頃より乗り物や工事現場が好きだった私にとって、巨大な船のドッグも非常に魅力的なところです。親切な三菱重工の方がドッグについても細かく説明をして下さいました。
1970年に完成した本牧のドッグは長さ370mで幅が60mであること。すべての海水を排出する時間が3時間であること。巨大な船を盤木という台にピタリと乗せるために、船の重さを計算してワイヤーで船を左右に前後に引っ張って微調整をしながら一日がかりで排水をしながらあらかじめ沈めておいた盤木に乗せることなど非常に興味深い話を三菱重工の方に伺いました。

本当に親切に素人の質問に答えて下さったので事情を伺ったら、ニッポン放送のリスナーでいらっしゃいました。「今夜もオトパラ!」もよくお聴きいただき、松本さんにもよろしくお伝えくださいと言っていただきました。
しかしなぜ私の顔がわかったのですかと聞いたところ、ラジオリビングをよく利用していただいていて、アナウンサーの顔写真が載ったカタログをみて知っていたとのこと。ちなみに松前漬けの大ファンとのことで、なんだかもう嬉しくなってしまったドッグ取材でありました。

三菱重工横浜艦船修理部の太田さん、本当にありがとうございました!
-

2025.12.19
小椋汐里さんのこと
当時、ニッポン放送報道部のニュースデスクだった上村貢聖さんは、東日本大震災の取材の過程で、会津若松の小学校で被災をし、その後福島市の視覚支援学校に進んだ小椋汐里さんと出会...
-

2025.12.13
小椋佳さんと上白石萌歌さんと女将
小椋佳さんの「ウルトラヒットの道標」の感想のメールを本当にたくさんいただきました。 「存じ上げている有名なエピソードですが何回聞いても面白い」 「小椋佳さんとはこのよ...
-

2025.12.05
小椋佳さんは超優秀な銀行マンでしたぁ
恒例の様々な電気的な設備を点検をするニッポン放送全館停電も無事に今年も終了いたしました。 日曜日の夜中から月曜日の明け方までに行われる大切な作業であります。 もちろん...
-

2025.11.28
久保さんのこと
「あさぼらけ」が始まった2016年の春に始まったのが乃木坂46新内眞衣さんの「ANN0」でした。 構成作家が古い付き合いの石川氏であったり、今私が所属している(株)ミッ...
-

2025.11.21
「笑福亭鶴瓶 2025落語会」in浅草公会堂
数年前までは「赤坂ACTシアター」で開催されていた秋の「笑福亭鶴瓶 落語会」ですが、 「ハリーポッター」の舞台がACTシアターで行われるようになってからは、 ここでは...