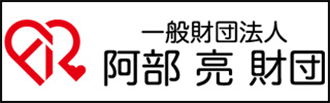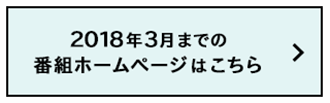【スタッフMの番組報告】
放送でもお伝えしましたが、先日発表された日本の小中学生の不登校の数が34万人で過去最多というニュースは
衝撃でしたね…。
理由はさまざまなようですが、コロナ禍を経験した子どもたちにとって、この時期は本当に大変だったと思います。愚息もその頃ちょうど高校3年間でしたが、正直、学校行事の記憶は親も子も皆無に近いです。
ですが、高校生くらいになると思考力や行動力も広いので、なんとかそれを乗り越えていましたが、初めてランドセルを背負う小1や初めて制服を着る中1のような子どもたちには、新しい環境ということにプラスの非常事態の環境がどれだけ酷なものだったか、想像しただけで胸が締め付けられる思いに、改めてなってしまいました…。
そんなコロナ禍も経験し、いま子どもたちの不登校は急増しています。
そうした不登校の子どもたちが、いつでもどこでもいつからでも学べる環境作りに取り組む団体をご紹介しました。それが、NPO法人多様な学びプロジェクトです。代表理事の生駒知里(いこま・ちさと)さんをゲストにお迎えしました。

右:NPO法人多様な学びプロジェクト 代表理事 生駒知里さん
年間5万人ペースで増えている不登校の子どもたちの受け皿には、民間のフリースクールや、学校内外に設置されている教育支援センターなどがあります。ですが、フリースクールの数は全国で700ほど、まだまだ足りているとは言い難い状況。そして何より、費用も3万~5万かかってしまうんです。
子どもが不登校になることで、食費もかかりますし、各ご家庭の出費はものすごい中、こうしたフリースクールに通うというのは、保護者の経済的、心理的負担は相当なもの、と生駒さんも話していました。
生駒さんご自身、7人のお子さんを育てるお母さん。そのうち、上の5人のお子さんが不登校になってしまったそうです。相談する場がない、子どものやりたい、知りたいを学校以外で作れる場がない…そうした不登校児の親として感じた生駒さんの思いが、「多様な学びプロジェクト」の活動につながっているんです。
街のとまり木プロジェクトでは、カフェや図書館など街の中に学校で居場所を失った子たちが気軽に立ち寄れる
場所を提供したり、不登校児の親と、専門家がオンラインでつながるコミュニティも開催。親が孤立しないことが
不登校の子どもたちの生きやすさに、とても大切であることを教えてくれました。
生駒さんの言葉でとても印象的だったのが、「子どもは真っ白い紙で、親が色を塗ってあげるものだと、ずっと思ってきたが、子どもが不登校になってみて、そうじゃないんだ、親が勝手に色を塗ってはいけないんだ、と気づいた」
というもの。
とっても優しくて、真面目な生駒さんのお母さんとしてのお子さんへの接し方がうかがえた場面でした。
それに気づいてから、子育ての考え方も変わってきたとおっしゃっていました。
子どもたちにとって、学校は新しい世界の連続ですが、親にとっても父・母の世界は新しいことの連続です。
それは、私も身に沁みて感じてきました。みんなと違う事に不安を感じ、悩み苦しむのは親も子も同じです。
「多様な学びプロジェクト」のような存在が、孤立しがちなそうした親子の救世主になっているんだな、と
強く感じた収録でした。
素晴らしい取り組みの数々は、HPをご覧ください。
次回も、「多様な学びプロジェクト」に迫ります。お楽しみに!
NPO法人多様な学びプロジェクト HP
https://www.tayounamanabi.com/