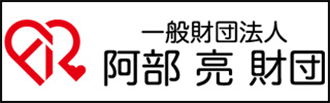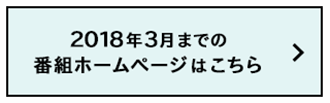【スタッフMの番組報告】
先日、近所の小学校のそばを歩いていたら、運動会の練習風景を見かけました。そこは数年前、愚息の通っていた
小学校だったので、「あれ?運動会って春じゃなかったっけ???」と疑問が浮かんでいたら、後日ママ友に聞いてみたら、最近の猛暑で、春先の運動会開催は学校側も断念して、秋に移行したのだと…。
とはいえ、9月、10月もまだ夏日があったり、外で元気に身体を動かして!!!と、一昔前の指導は学校現場でも難しくなっているのだな…としみじみこの数年での変化を感じました。
(春や秋というなんか中間な季節、私は結構好きなので感じる時間が減るのは少し悲しいですね…)
さて、10月2週目のゲストは、大分県大分市にあります、大分工業高等専門学校の足踏みミシンボランティア部という課外活動で指導をしている岩本光弘先生でした。

真ん中:大分高専足踏みミシンボランティア部部長 高野日彩さん右:岩本光弘先生
高専というのは、中学卒業後、専門知識(主に技術系)を学ぶ5年生の高等教育機関なんです。卒業後は、エンジニアとして就職したり、大学に編入してさらに学びを追求したり、日本の未来を担う技術者の卵が集っています。
ですので、学生は16歳~20歳が基本的には多く、2週目の放送で登城する部長の高野さんは20歳でした。
足踏みミシンボランティア部は、その昔、日本で嫁入り道具でもあった足踏みミシンがまだ家に眠っている方々から譲り受けて、修理をし、フィリピンの貧困層地域などに贈り届け、現地にも赴き、使い方や修理方法の指導も行っているんです。
岩本先生はこの活動を20年近く見守り、単にミシンを修理するだけではなく、それを現地で使う人々の思いや現地の暮らしに触れることで、学生が大きく成長していく、と嬉しそうに語っていました。
フィリピンの貧困層地域では、雨季で農作業ができないとき、足踏みミシンが大活躍しています。電気も必要としないので、足踏みミシンで縫製品を作って安定した収入源にできるというわけです。
平和な日本に暮らす日本の高校生が、衣食住のすべてを日々懸命に自分たちで支える東南アジアの人達の暮らしを
知るということは、何にも代えがたい経験ですよね…。本当に素晴らしい活動だと思います。
昨今の物価高で、ミシンを送る輸送費や、部員が現地に行く渡航費を確保することがとにかく大変だと、話していた岩本先生。クラウドファンディングにも挑戦し、成功したばかりですが、この先の不安は尽きないそうです。
こうした日本の学校の課外活動が、世界の貧困層地域の生活の助けになっているというのは、誇らしいです!
多くの課題や困難なこともあるかと思いますが、これからもぜひがんばって後世に引き継いでいってほしいです!
次回は、高野部長と岩本先生に登場いただきます!
来週は特別番組でお休みで、次回は10月28日の放送です。
お楽しみにー!
大分工業高等専門学校足踏みミシンボランティア部HP
https://www.oita-ct.ac.jp/2024/05/22/20240520_sewing-machine_cf/