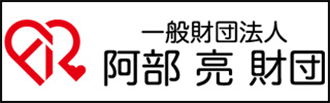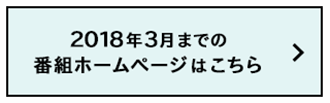【スタッフMの番組報告】
突然ですが、みなさんは街を歩いていて、イラっとすることはありますか?
ちなみに私は、一つあるんですよねー。
それは、ペットボトルのゴミ箱の穴になっているところに、缶やほかのものが突っ込んであって、捨てられない
時です・・・。
わかるわかる!とうなずいてくださる方がたくさんいたら嬉しいのですが、と同時に共感多数であればあるほど
よく目にする光景ということで、大問題ですよね。
自分の出したゴミくらい、きちんと決められたところに捨てましょうよー、という思い、多くのみなさんは持っていると思いますが、それだけにとどまらず、こうしたゴミ問題をはじめ、あらゆる環境問題を、科学技術の力で克服する事をミッションに活動しているベンチャー企業があるんです!
それが今回のゲスト、株式会社「ピリカ」代表取締役の小嶌不二夫(こじまふじお)さんです。
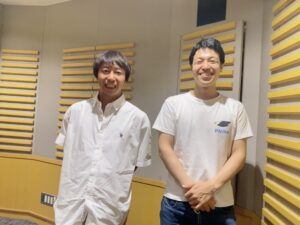
右:株式会社「ピリカ」代表取締役 小嶌不二夫さん
写真でもわかるように、とにかく、終始にこやかな小嶌さんのお話は、本当に明朗快活でわかりやすく楽しいものでした!
ゴミ問題をはじめ環境問題というと、どうしてもかたい、私の苦手な理数分野の話が満載かと思っていたのですが、恥ずかしながら、こんなに長く生きてきて、初めてきちんと今の日本や世界で起きているゴミ問題について真剣に考える時間となりました。お聴きいただいた方もきっとそうだったのでは!
まず、小嶌さんがゴミ問題に関心を持ったきっかけが面白いんです。
7歳の小嶌少年は、小学校の図書室で出会った「地球の環境問題シリーズ」7冊にとにかく影響を受けて、環境問題を大きなやっつけないといけない怪獣みたいに思えた、と言いますから、その視点、発想が小嶌少年すごいです!!
そこから高校、大学、大学院と進学していく中でもその思いは続き、研究者になる道を選んだのです。ただ、大学院で研究をしていくうちに、研究者では、論文を書くところで終わってしまい、問題解決までたどり着けないという現実に直面したとか・・・。
そこで、ビジネスとして環境問題に取り組めないか考えながら、世界一周をしているうちに、ゴミ問題が、先進国、途上国関係なく共通で重要な課題だと気づかされ、冒頭にも書きましたが、科学技術の力でゴミ問題を解決しようと思い立ち、帰国後に大学時代の仲間と共に、ゴミ拾いのSNSアプリ「ピリカ」を開発して、2011年に会社を作ったという、いわば環境問題の現代革命児なんですね!
ここまでの発想、行動力、実行力だけでも素晴らしいです。
このゴミ拾いのSNSアプリ「ピリカ」なんですが、どういうものかと言いますと、「ゴミ拾いの世界のツイッター」なんです。
スマートフォンで誰でもダウンロードできるアプリで、例えばゴミを拾った場所やものを投稿し、仲間同士でコミュニケーションを図れるんです。具体的には、ゴミを拾った者に対して、イイネのかわりに「ありがとう」ボタンを押すかんじです。
自分の住む街、働く街をいまどこかの誰かがゴミを拾ってきれいにしてくれる、そのことへの感謝の「ありがとう」、ここでゴミ拾いをしたよーと呟いた人は、自分の社会貢献活動が可視化され、少しいいことをした気持ちになる、この当たり前なようで当たり前にできにくい、でもとても大切な温かい思いと行動、これをアプリ一つで解決してくれるのが、「ピリカ」なんですねー。
SNS全盛のこの時代、「映え」にだけこだわって何かを投稿するのもいいですが、人のために、自分のために「ゴミ拾い」という世界共通のわかりやすい活動を投稿して、世界中でその素晴らしさやきれいになっていく達成感を共有するのもいいですよね。
これならば、今の若者たちにもささっていくなーと実感しました。現に、高校3年生の息子に、ピリカの話をしたら、すぐにダウンロードして、若干ゲーム感覚ではありますが(汗)、興味深々でした。
SNSで広まって、今では世界100か国以上、延べ200万人以上がアプリを通じて清掃活動に参加しているそうです。
さらに、ポイ捨てゴミがどんな場所にどれくらいあるのかを調査する「タカノメ」というサービスも開発されていて、これは、路上を撮影して、映っているゴミを画像解析することで、喫煙場所の設置場所を検討したり、清掃ルートの見直しをするのに活用しているんです。
多くの自治体や企業から調査を依頼されて、この事業も収益化が始まっているという、勢い止まらぬ「ピリカ」の事業力ですね!
「タカノメ」は言うならば、ゴミの分野の「アメダス」を目指していると語る、小嶌さんの目は、おそらく7歳の小嶌少年の頃から変わらないであろう、真っすぐに夢を追う人の目でした!
番組の後半では、今世界中で問題となっている海洋プラスチック、マイクロプラスチックの調査にも乗り出した話もされていました。
その中で、「2050年には、海を漂う魚の量よりも海を漂うプラゴミの重量の方が上回ると予測されている」という話が飛び出し、ビックリしました。小嶌さんもおっしゃていましたが、このまま海洋ゴミを放置したら、魚が身動きができないほどのプラスチックで海が覆われてしまうというのは、衝撃的でした。
そもそも船でプラスチックをとりに行くとコストがかかるので、流出源を見つけるために、自前で調査装置を作ったのが「アルバトロス」というものなんです。さすが、京都大学の研究室から生まれた「ピリカ」の底力!
ないものは、自分たちで作ってしまえ!志高い集団ゆえの発想力です。
しかも「アルバトロス」で調査した結果、プラスチックの20%は陸から流れ込んだ人工芝の破片だということもわかったそうです。これまた、調べてみないとわからないですよねー。
ひとつひとつの施設をグーグルマップを使って人工芝を使っているか調べて、どこからどれくらい流出しているか、そんな地道な調査、すごすぎます。
それでも、『気合と根性はコストが安いですから!」と笑い飛ばす小嶌さんは超人の域ですね(笑)
ゴミ拾い、というものは我々が幼稚園、小学校、そんな幼いころから当たり前に学んできた活動です。
でも大人になるにつれ、ゴミが転がっていても、率先して拾うことも少なくなったり、拾ったとしても、いいことをしたことをひけらかさないのがいいこと、みたいに考えるのが日本人特有の共通感覚だ、ということもよくわかりました。
「手をとめて、ゴミをひとつ拾いましょう!」
最後の小嶌さんのリスナーのみなさんへのメッセージこそ、地道な活動の大切さを知るこの番組のテーマとも通じる気がして温かい気持ちになりました。
私も、日々、落ちているゴミに手を伸ばせるような人間に・・・、精進いたします!
株式会社「ピリカ」の様々な取り組みについて、詳しくお知りになりたい方は、公式ホームページをご覧ください。
https://corp.pirika.org/

次回の放送もお楽しみに!