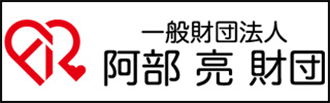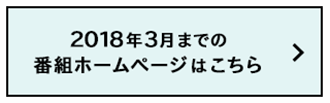京都精華大学准教授 ナンミャケーカインさんとパーソナリティ阿部亮さん
ミャンマーの軍のクーデターから4か月あまりが過ぎました。
この間、犠牲になられた市民の方は900名近く、拘束されている方も5000名以上と言われています。
現在は軍とタイ国境の少数民族武装勢力との戦闘で、一般市民の巻き添え、多数の避難民が増えています。そのほとんどが生活困窮に陥っています。
また、ヤンゴン市内では爆発騒ぎが続いていたり、銀行も閉まっており現金不足も起こっています。(ATMは常に長蛇の列…)
そして、ミャンマーでは、昨年コロナ対策で休校していた学校ですが
例えば大学、5月から軍が一方的ともいえる開校を決めましたが、大学の教員や生徒のほとんどが 国軍への抵抗、反意を示し、戻っていない状況です。
6月1日からは小学校から高校までの公立学校も軍により一方的に再開しましたが、
こちらも同様で、ミャンマー全土の半分の教師がCDMを行っており、職務復帰を拒んでいて、また、保護者も子どもを学校に行かせません。
しかし軍はこういったCDMをする教職員を指名手配したり、懲戒処分したり、締め付けをしています。
(抗議教員15万人停職、日本経済新聞 5月26日付)
クーデターを起こし、国を破壊しているともいえる軍。
国の未来を作るのは子どもたちなのに、軍がしていることは、子どもへ恐怖を与え、成長の機会を奪っている、そう思わざるを得ません。
よくミャンマー人から聞くのは、「ミャンマーの教育を変えたい」という話。
軍政時代の教育は「思考しない、暗記教育」
先生が「白」と言えば黒いものでも「白」と言わなければならない…

今回は大学の講義のため、リモートで参加いただきました。
解答欄に自分の意見を少しでも書いたら「×」になる…
そんな軍政教育がずっとあったミャンマーですが
2011年以降民政移管、2015年NLD政権の誕生後は どう変化したのでしょうか。
ミャンマーでは2015年以降、情報も自由に手に入れられるようになり、
SNSも盛んになって、世界のニュースも手に入り、自由な発言も許された。
表現の自由、民主主義、個の自由、もう後戻りはしないと、市民が考えるのは当然です。
必ず民主化を勝ち取り、自分たちの国の未来をつくろうとするミャンマー人の思いの底にはやはり教育を変えたいという思いが。
21日の放送では、軍政時代の教育も受けた経験のある 京都精華大学准教授のナンミャケーカインさんにお話を伺います。
「横浜パンフレットキャンペーン」桜木町駅前で 週末の土日どちらかやっています。
ミャンマーの状況を知りたい!応援したいと思ったら、お近くの方はぜひお立ち寄りくださいね
https://www.facebook.com/Yokohama-Pamphlet-Campaign-Myanmar-100945265485860

ナンミャケーカインさん。ミャンマー情勢に関するオンラインやウェビナーでも登壇されています。また「横浜パンフレットキャンペーン」といって、毎週末、横浜桜木町でミャンマーの現状を伝えるパンフレットを配る活動もされています。