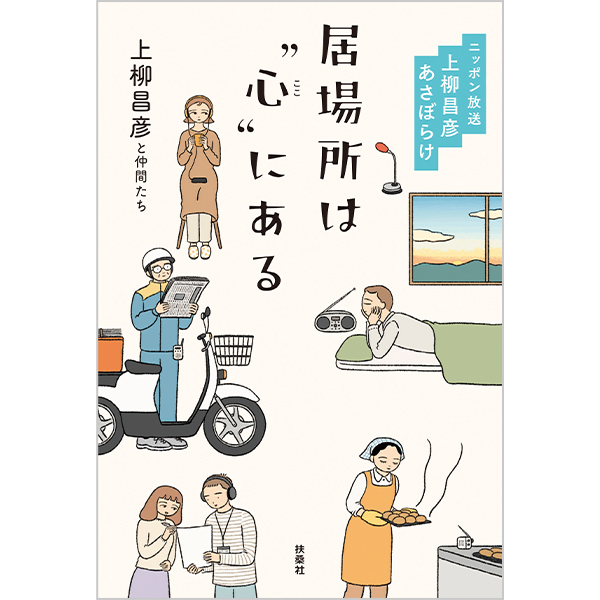史実と物語の難しさ
NHKのドラマに登場した人物の言動が事実と異なると、ご遺族が抗議の声を上げています。
問題となっている作品は8月16日と17日に放送された「シミュレーション~昭和16年の敗戦」で、原作は1980年代に「昭和16年の敗戦」として出版された作家の猪瀬直樹さんの作品です。
文庫本になった際に私も読みましたが、1940年に内閣総理大臣直轄の「総力戦研究所」という組織を立ち上げ、アメリカと戦争をした場合に日本はどうなるかを当時の官僚、軍人、通信社の若手が集い様々なシミュレーションを行ったというノンフィクション小説です。(ノンフィクションとはいえ総力戦研究所は実際に存在した組織です)
結果、日本はソ連の参戦もあり食料、燃料など国力が持たず必ず負けると結論付けます。
しかし当時の内閣は机上の空論であるとしてこれを退け開戦へ突入。
原爆投下だけは予測できなかったものの、事態はシミュレーション通りに展開しました。
この総力戦研究所の所長はNHKドラマでは若手の意見に批判的で圧力をかける陸軍中尉として描かれていましたが、中尉のご遺族が祖父は(中尉は)研究所内で自由にものを言える空気を作り出した人でありドラマは事実と異なると訴えています。
NHKは「これはフィクションである」と最後にテロップを流し、その後にドキュメンタリーとして事実を放送したとしています。
私もオンエアーを観ていましたが、若手の意見をつぶす役という印象だけが残っていて、残念ながらドキュメンタリーの部分の記憶があまりありません。(NHKプラスの配信は終わっていて確認が出来ません)
ご遺族はBPO(放送倫理・番組向上機構)に申し立てを行う意向との事なので今後の展開を注視しようと思います。
今回の映像作品を制作する際の「史実と物語」の問題について映画「雪風YUKIKAZE」のプロデューサー小滝氏から話を様々聞きました。
小滝氏と脚本の長谷川康夫さんは2011年に映画「聯合艦隊長官 山本五十六」の脚本を作る際に原作の半藤一利さんから
「物語なのだから、事実をしっかりと把握した上なら、あえて捜索する部分があっても構わない。しかし無知を自覚せずに、都合よくフィクションをはめ込んではいけない」という言葉を受け取ります。
以来、二人は多数の作品を世に送りだしていますが、この言葉を忘れることなく資料や関連書籍、関係者の証言に徹底的に接することを続けています。
そして今回の映画「雪風 YUKIKAZE」では、旧海軍の中枢の人々が交わす会話や、駆逐艦の中での作業や服装、所作など膨大な資料を参考にして数年かけて準備を重ねました。
一方で先任伍長と妹、艦長の妻と義理の父の会話などは物語なのだと思います。
それでもいわゆるミリタリーに詳しい方々からはあの海戦にはあの艦船はいなかった、旧海軍はあのようなフランクな人間関係ではなかった等の厳しいご指摘も届いているそうです。
艦船の参加不参加に関しては多少の物語はあったようですが、
人間関係については乗組員の方々の証言が多数残っていて
それらを参考にしているそうです。
(艦船によって艦内の雰囲気が異なりそれを「艦風」と言います)
また旧海軍の乗組員があのように髪を伸ばさず皆丸刈りであったろうし、帽子をあみだにかぶることはなかったはずという指摘もありましたが、それに関しては当時の写真が膨大な量残っていてそれらを参考にしたとのことです。
まぁヘアメイクさんは乗っていなかったのであんなにシュッとした感じではなかったでしょうが、なにせ長い航海で皆さん髪は伸ばしっぱなしで風呂にもほとんど入れなかったとの事。
乗員3300人の戦艦大和には20人ほどが入れる風呂がいくつかあったそうですが、剰員300人ほどの駆逐艦には3人ほどが入れる風呂が一つあっただけで上級将校は別として若い乗組員はほとんど入れなかったそうです。
(ちなみに海水を沸かしたので石鹸は泡立たない)
だから史実にもっと忠実にするならコーヒーで黄ばみや汚れをつけた衣装は、もっと悲惨なものだったかもしれないと小滝氏は言っていました。
また船が攻撃を受けて沈んださい、船から流出した重油で真っ黒になった海に乗組員が放り出されるイメージがあったのですが、
そういった状況にはあまりならなかったそうです。
しかしサメが彼らを襲い、海が真っ赤に染まっていたという証言は多々あったけれど、映画ではさすがにその表現は避けたとも聞きました。
今回、映画「雪風YUKIKAZE」の公開に多少なりともかかわったことで「史実と物語」の難しさや映画製作の気が遠くなるような苦労を断片ではありますが知ることが出来ました。
またリスナーの皆さんが多数の感想を寄せて頂いたことにも心から感謝申し上げます。
そして「映画の最後に声の出演であんたの名前が出てきたけれど、どこでしゃべっていたんだ?」というご意見も多数でした。
目立たぬように気配を消して読んだことがうまくいったと、自分で自分を褒めております。
-

2026.01.30
竹下景子さんとともに夢のラジオドラマを!
毎日深夜にニッポン放送に来るタクシーの中でのお楽しみはラジコでオールナイトニッポンを聴くことです。 「60代の後半になっても月曜深夜から木曜深夜、午前1時から4時半まで...
-

2026.01.23
大竹しのぶさんの「ピアフ」を観て
先日、日比谷シアタークリエで大竹しのぶさんの「ピアフ」を観劇してきました。 大竹さんに関しては昨年に3月に「やなぎにツバメは」を新宿紀伊国屋ホールで、7月には新橋演...
-

2026.01.16
久米宏さんのこと
久米宏さんの訃報には、ただただ呆然とするのみでした。そして仕事仲間に久米さんの想い出を語っているうちに目頭が熱くなってしまい、それを悟られないようにフッと横を向いてごまか...
-

2026.01.09
スタジオからあなたにお電話を物語
今さら年末年始の話をしても仕方がないのですが、年末年始の通常の生放送と「ラジオ・チャリティー・ミュージックソン」のアシスタント、30日11時からの「あの素晴らしい歌をもう...
-

2026.01.02
45年目と10年目、直接御礼を申し上げたく!
暮れから正月にかけて平常運転で生放送をお送りいたしました。 気が付けば2026年。 なんとマイク生活も45年目に入りました。 80年の秋に就職試験を受け、アナウンサ...