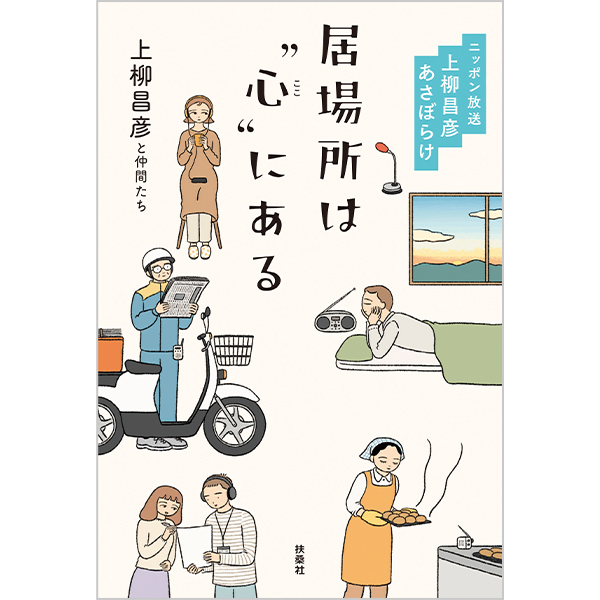またまた良い映画に出会えました
ゲストの収録が重なってくるとかなりの時間、資料の読み込みやインタビューの内容を考えてしまいます。
そうなると不器用なもので映画やドラマや配信を観る時間が無くなります。
私の数倍は忙しいであろうTVプロデューサーの佐久間宣行さんは毎日時間をどうやりくりして多くのエンタメをチェックしているのかその秘訣を伺ってみたいとすら思ってしまいます。
先日はゲスト収録がなかった3日間で5本の映画を観ました。私の体があの暗闇を求めていたのです・・・
「野生の島のロズ」「大きな玉ねぎの下で」は放送でも感想を話しました。「リアル・ペイン」「誰よりもつよく抱きしめて」はまたの機会に紹介したいものです。
映画を番組で語るとしばしば「内容を話しすぎるのでやめて欲しい」というご意見を頂きます。
こういう方が浜村淳さんの番組をお聴きになったらラジオを壁に投げつけてしまうかもと思います。(冗談です)
まぁ「ネタバレ警察」的な人は意外と映画を観に行っていないと思わないでもないのですが、実は私の場合映画に関する話は事前に公開されている内容のさらにそのずっと手前で止めるようにしているのです。
様々な映画評に目を通し、どこまで内容が書かれているかを調べて、ではどこで話を切り上げるかを毎回考えます。
まぁストーリーのほんの序章だけを語りさてその後は映画館で是非!という感じなのですね。
とは言え昭和30年代には日本人は1年に12本の映画を観ていましたが、今では1年に1本弱になっているのが現状です。
番組で映画を取り上げると「観ました!よかったです!」というメールをよくいただくのですが、それは極々少数のありがたい方々なのでした。
ですからわざわざ観には行かない大多数の方々のために、浜村淳さんのように内容を最後までほとんど語りきってしまうことこそ親切なのかもしれませんねぇ。
すいません!ちょっと愚痴っぽくなったのでもう一本観た映画の話など。
14日の5時台の放送でもお話した作品です。
それはドキュメンタリー映画「小学校~それは小さな社会」という映画で、イギリス人の父と日本人の母を持つ山崎エマ監督作品です。
大阪の公立小学校で学び中高は神戸のインターナショナル校、そしてニューヨーク大学で映像を学んだ山崎監督。
アメリカの仲間から本人は当たり前のように生活しているのに「責任感が強いね」「いつも時間をきちんとまもるよね」「勤勉だよね」とやたらと驚かたそうです。
それはもしかして日本の小学校に通ったからではないかと思い、6年かけて世田谷区の公立の学校と交渉し、2021年の1年間、150日間で700時間かけて教室、児童会、行事、校庭、廊下、職員室、通学路、家庭で撮影を行いました。
時期はコロナ禍で緊急事態宣言が発令の頃、中止も考えた中で生徒や先生や親の小さな表情の変化や小さなつぶやきとため息、後姿などを丹念に追っています。
一年に1本映画を観るか観ないかという方にもぜひ映画館に足を運んでいただきたい作品です。
顔だけでなく名前も出すことを行政や学校がよくぞ承諾して下さったと心から感謝を述べるとともに、生徒のひたむきさや先生方のご苦労が画面から伝わってくる一方で、正解はこうであるととても軽々には語れない、日本における教育というあり方を深く考えさせられる映画でした。
ドキュメンタリー映画なのでネタバレというのも妙ですが、詳しい内容に関してはほとんど書いていないのでご安心の程を・・・
-

2026.01.30
竹下景子さんとともに夢のラジオドラマを!
毎日深夜にニッポン放送に来るタクシーの中でのお楽しみはラジコでオールナイトニッポンを聴くことです。 「60代の後半になっても月曜深夜から木曜深夜、午前1時から4時半まで...
-

2026.01.23
大竹しのぶさんの「ピアフ」を観て
先日、日比谷シアタークリエで大竹しのぶさんの「ピアフ」を観劇してきました。 大竹さんに関しては昨年に3月に「やなぎにツバメは」を新宿紀伊国屋ホールで、7月には新橋演...
-

2026.01.16
久米宏さんのこと
久米宏さんの訃報には、ただただ呆然とするのみでした。そして仕事仲間に久米さんの想い出を語っているうちに目頭が熱くなってしまい、それを悟られないようにフッと横を向いてごまか...
-

2026.01.09
スタジオからあなたにお電話を物語
今さら年末年始の話をしても仕方がないのですが、年末年始の通常の生放送と「ラジオ・チャリティー・ミュージックソン」のアシスタント、30日11時からの「あの素晴らしい歌をもう...
-

2026.01.02
45年目と10年目、直接御礼を申し上げたく!
暮れから正月にかけて平常運転で生放送をお送りいたしました。 気が付けば2026年。 なんとマイク生活も45年目に入りました。 80年の秋に就職試験を受け、アナウンサ...