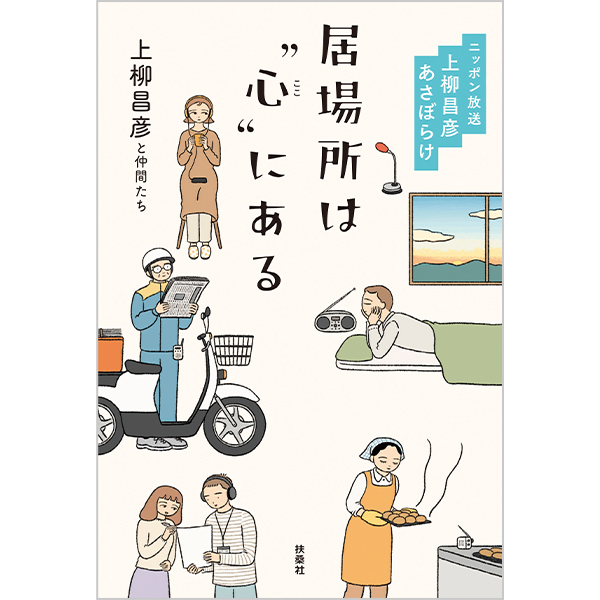災害とラジオ
今から100年前、日本ではまだラジオ放送は開始されていませんでした。
歴史に「もし」はありませんが関東大震災の発災時に愛宕山の東京放送局(今のNHK)から放送が流れていたらと想像をすることもあります。
1925年3月の開局当時でラジオ受信機は3500台、7月末には45000台、年末には10万台という記録が残っていますが、火災にともなう停電も発生したでしょうから放送を送り出すことも受け取ることもなかなか難しかったかもしれません。
しかしこの大地震が日本ラジオ開局を早める一つの要因になりました。
開局当時のプログラムはニュースや株式市場、米などの相場などが中心で、その後歌舞伎役者によるラジオ劇(いわゆるラジオドラマ)など娯楽番組といわれるものも生放送で送出されたようです。
ラジオ劇では歌舞伎役者が坪内逍遥や徳富蘆花、尾崎紅葉などの作品を演じていましたが、1925年8月3日の夜にイギリスのBBCで放送された作品を小山内薫が翻訳し演出した「炭鉱の中」というプログラムが放送されました。
落盤で炭鉱に閉じ込められた男女の絶望的な恐怖、そこに救助の手が徐々に近づいてくるが、さて!という内容です。
炭坑内に響く不安げな声、落盤の轟音、流れる水、遠くから呼びかける救助隊の声、これらを多くの役者と効果音を演技に合わせて作り出す音効という職人さんたちが一つのスタジオ内で作り出した作品です。
そしてこの生放送が行われる直前にアナウンサーが「この放送は部屋の明かりを消してお聴きください」とアナウンスしました。
その時、当時は海が見えたという愛宕山の社屋から、街の明かりが一つまた一つと消えていく様を職員たちが見て、自分たちの放送は本当に視聴者のところに届いていることを実感し感動したという記録が残っています。
この事実を学生時代に知り、私のラジオへのあこがれがますます強くなったのでした。
「ラジオと災害」と語られますが、ドラマの世界では創成期から、災害が描かれていました。
また「部屋の明かりを消して」はその後、ANN月曜2部で新宿ワシントンホテルのスィートルームから、何人ものリスナーがくるくる回す懐中電灯を見ることにつながって行くのでありました。
この件に関しては拙著「定年ラジオ」にも書かせて頂きました。
-

2026.02.06
ラジオドラマの感想とイベントと
竹下景子さんとのラジオドラマ、いかがだったでしょうか。 目の前で4役を演じ分ける竹下さんの表情が変化する様が、なんともチャーミングで魅了的でありました。 それに引き換...
-

2026.01.30
竹下景子さんとともに夢のラジオドラマを!
毎日深夜にニッポン放送に来るタクシーの中でのお楽しみはラジコでオールナイトニッポンを聴くことです。 「60代の後半になっても月曜深夜から木曜深夜、午前1時から4時半まで...
-

2026.01.23
大竹しのぶさんの「ピアフ」を観て
先日、日比谷シアタークリエで大竹しのぶさんの「ピアフ」を観劇してきました。 大竹さんに関しては昨年に3月に「やなぎにツバメは」を新宿紀伊国屋ホールで、7月には新橋演...
-

2026.01.16
久米宏さんのこと
久米宏さんの訃報には、ただただ呆然とするのみでした。そして仕事仲間に久米さんの想い出を語っているうちに目頭が熱くなってしまい、それを悟られないようにフッと横を向いてごまか...
-

2026.01.09
スタジオからあなたにお電話を物語
今さら年末年始の話をしても仕方がないのですが、年末年始の通常の生放送と「ラジオ・チャリティー・ミュージックソン」のアシスタント、30日11時からの「あの素晴らしい歌をもう...