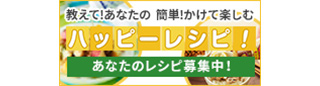2025.09.05
「令和6年能登半島地震」から、1年9か月。西出牧場・西出穣さんのお話
9月5日(金)、一之輔ハッピーでは、
西出さんは、ニッポン放送をよく聴いてくださっているリスナーさんで、
石川県能登町で、西出牧場を営む西出穣さんにお電話をつないで話を伺いました。
西出さんご一家、そして、営む牧場は
2024年1月、発生した「令和6年能登半島地震」の被害を受けました。
あれから、1年9か月。
現在の状況、復興の道のりの険しさ、地震の後のご家族の様子など、
西出さんが、詳細にまとめてくださった文章を掲載します。
ご協力いただいた西出牧場の西出さん、御礼申し上げます。
ありがとうございました。
――――――――――――――――――――――――――――――――
◎能登の大地震から1年と9か月、あの時の事は今でも鮮明に
・震災直後の我が家のこと
震災が起きた1月1日は妻と子ども達は長野県の妻の実家に帰省中だった。発災直後、妻の実家から安否確認の電話があった時、娘が「私の机にあるグミ食べていいよ!あるもの何でも使って!」と言うと、息子も「僕の貰ったマリオのカップ麺も食べていいよ。グミとチョコも僕のだけど食べていいよ!」と言ってくれた。子ども達の心配する気持ちがうれしかった。
妻と子供たちはすぐに能登に帰ろうとしたが、新幹線も止まり、能登へ続く主要な道路も壊滅的な被害を受けどの道が通れるかもわからない状況。後にわかった事だが、金沢から能登まで普段なら1時間半で行ける距離が10時間もかかる状況だった。また、自宅が大きな被害を受け住める状態ではなかったため能登へ戻ることを当面あきらめ、長野での避難生活が始まった。子ども達は一時的に妻の実家近くの小学校に転校させてもらったが、宅配便も止まっていたためランドセルや学用品を送ることもできず、子ども達は紙袋にノートや鉛筆を入れて通学した。普段はスクールバス通学だったので、避難先での徒歩での通学は新鮮だったと言う。
◎当時の子供への行動・体験は
・学校の動き
・校舎も被害を受けており、避難所として多くの人々が身を寄せていた。
・1月5日。3学期の開始は当面延期と学校から連絡がまわる
・1月15日。子ども達の不安を少しでも和らげるために学校でかるたやトランプなどのレクレーションをする時間を先生たちが作ってくれた。
・1月22日 学校再開。3学期が始まる。通学が困難な児童のためにオンライン授業も実施された
・私が見た被災地と子ども達のこと
避難所の環境は過酷だった。私の地区は数時間で停電が解消したので明かりがあるだけでも不安は和らいだ。しかし断水は堪えた。まず、どこの避難所もトイレの状態が悪化した。私の地区の公民館は山の水や地下水が使えるので、バケツで汲んだ水でトイレを流せたが、一部の避難所ではトイレの環境が著しく悪化した。しかも停電している暗い中でこの状態は大人でも耐えがたい環境だ。また、暖房も不足しており、大人だけなら我慢できても子どもも一緒だととても避難所では生活できないと、多くの子供連れの家族が自宅や車中泊で乗り切り、金沢への二次避難を早々に決めた人たちもいた。
子どもと一緒に避難所に行くと他人に迷惑をかけてしまうからと、近所の酪農家家族も避難所に行かず、牛舎の倉庫で避難生活していた。停電は1週間程度で解消した地域も多かったが、断水は長期化し長いところは5月までかかり、我が家も断水が解消したのは4月11日だった。震災後、能登の中学生が金沢などへ集団避難することが話題にもなったが、長期間水道が使えない中、小さい子供がいる家庭の苦労は大きく、昨年1年間で中学生以下で約1000人以上の子ども達が能登から他地域に転出してしまった。
そんな中、自衛隊の入浴支援(仮設風呂、自衛隊風呂)は大変ありがたかった。毎日復旧作業に追われ先の見えない不安な日々で唯一ホッとできる時間だ。自衛隊の風呂に入っていると小学生の男の子たちが入ってきた。男の子たちは、お互いのイチモツを見せ合いながら、どっちが長いかと盛り上がっていた。子ども連れで自衛隊風呂に行くと迷惑がかかるのではないかと遠慮してしまう人もいたようだが、こうやって子ども達が無邪気にはしゃぐ姿を見て私はほっこりした気持ちになれた。
近所で息子の同級生にあったとき、「〇〇くんいつ帰ってくる?元気で帰ってこないとぶっとばすって言っといて」と言われた。子ども達も楽しく遊んでいた日常が変わってしまい、さみしさ、怒り、悲しみなど、やり場のない思いに必死に堪えてると感じた。
◎能登はどうですか?
被災家屋の公費解体も進み、町の中は驚くほど更地が多くなった。そして、更地となった場所に新たな住宅の建設も始まっており、能登全体が建設ラッシュといった様子である。
能登では応急復旧から本復旧へとフェーズが進んでいる。震災後、砂利をひいただけ、簡易的な舗装をしただけの道路は、交互通行や通行止めで本復旧工事をしているため、昨年より移動には不便も伴うが、能登が復興に向けて進んでいる前向きな不便さでもある。
ようやく一部のコンビニが24時間営業を再開した。最近までコンビニは朝の6時から夜10時までだった。
仔牛たちの牛舎の公費解体が終わり、先日牛舎新築工事の契約をしてきた。来月から新築工事が始まる。搾乳牛舎の屋根もようやく工事が始まり雨漏りから解放されるまであと少しになった。
今年の1月1日に、飯田アナウンサーが中継をした珠洲市飯田地区。この飯田地区にある飯田小学校で来月、全国から酪農家有志が集まり子ども達に牛とふれあう機会をとおして笑顔になってもらう事を目的とした被災地支援特別授業、「わくわくモーモースクール」を開催予定だ。この授業最大の特徴は本物の牛が学校にやってくること。そして、当日子ども達に乳しぼり体験をさせてくれる牛が、師匠が名付けてくれた、「チェリー プレジデント ヒワラ」である。当日はヒワラ様の移動に大型のチャーター便(家畜専用車)を予約した。エグゼクティブ ビューティー サヤカの叔母として生まれた仔牛も一緒に連れていく。チェリー プレジデント ヒワラが飯田小学校の子ども達に笑顔を届けます!
◎子供をもつ親へ
避難所での生活は想像以上に大変だと思いますが、命を守ることが第一なので、周りの迷惑とか考えずにまずは避難することが大切です。避難所で友達に会えればお子さんもホッとできると思います。
避難所では子どもさんの食べられるものが少ないかもしれません。余裕があれば、日頃から子どもさんの好みの食べ物を用意しておくといいでしょう。また、日頃から非常食を買っておき(アルファ米や缶詰のごはん、非常用レトルト食品など)時々入れ替えするタイミングで実際に「非常食を食べてみる」ことを子ども達と経験しておくといざという時に役立つと思います。
災害時、非常食だけでは栄養も偏りがちになるので、栄養豊富な牛乳をぜひ飲んでください。ただし、通常の牛乳は冷蔵保存が必要ですが、震災などでは停電がつきものです。そこで便利なのがロングライフ牛乳(LL牛乳)です。これは140℃で超高温瞬間殺菌された常温存可能な牛乳なので、災害で停電した時でも安心して飲める牛乳です。
賞味期限も2か月~4か月と長いので、ローリングストックしておくことをお勧めします。
また、発災後は支援者やボランティアの方だけでなく、窃盗を働こうとする者や不審者が現れることもあります。大規模な災害が起きると全国から警察が集まってくれて被災地をパトロールしてくれますが、発災から時間がたち警察が撤収していくと、子ども達への声かけ事案などもありましたので、不審者へも十分な注意が必要だとお子さんに話しておくことが被害を未然に防ぐことになると思います。
≪以下、参考までに≫
震災が起きた1月1日は妻と子ども達は長野県の妻の実家に帰省中だった。震災が起きた時のことを長女(当時小5)と長男(当時小1)は次のように話している。
・長女(当時小5)
【地震の起きた時のことを教えて】
長野で揺れた時、揺れの大きさにびっくりして机の下に隠れるので精いっぱいだった。
すぐにテレビをつけて地震の情報をみたとき震源が能登だとわかって、すごく怖かった。津波が来るんじゃないかとか、家が大丈夫かとか、能登の友達が無事か心配だった。
壊れた家の写真を見てショックだった。次余震が来たら潰れちゃうんじゃないか、すごく心配だった。
【能登に帰れないってわかった時のことは?】
学校のこと、授業のことが心配だった。
【能登の学校に通えなくなったから、長野の学校に行けることになった。その時の気持ちは?】
初めて登校するまでずっと緊張していた。でも、教室にいったらクラスの子たちが沢山話しかけてくれた。学校のことも教えてくれて、一気に緊張もほぐれていった。浅間山が近くにある学校だったから、噴火に備えてヘルメットを被っての登下校が能登だとありえないことだったから逆に楽しかった。
【能登に帰ってきた。震災後の能登をみてどう思った?】
被害の大きさにびっくりした。道路がいたるところで崩落していて、元の町の景色がわからないほど家がつぶれていて、家に住んでいた人たちが無事なのか心配になった。
【たくさんの人たちが支援してくれたけど、心に残っている支援は?】
自衛隊のお風呂で、隊員さんがくれた梨味のグミがすごくおいしかった。
・長男(当時小1)
【地震が起きた時のことを教えて】
揺れた時、家が回転するように揺れて怖かった。アトラクションで酔った気分。
自分たちの住んでいるところで大きな地震が起きてびっくりした。不安だし、心配だった。自分たちが住んでいた家がひどい壊れ方をしていて、これから自分の住む家がなくなるんじゃないかという心配があった。能登の友達のことが心配で、いつも一緒に遊んでいた子の家の裏が山だったから土砂崩れが起きていないか心配だった。
【長野の小学校に通う事になった時の事】
長野の学校が初めてで、地元の友達もいないから不安だった。実際に学校に行ってみたけど、緊張がとれなくて先生の声も友達の声も入ってこなかった。お姉ちゃんはすぐに学校に慣れたけど、自分は慣れるまで2か月くらいかかって、慣れてきたころに能登に帰ることになった。
【能登に帰ってみて】
前の能登と違ってびっくりしたし、道路もたくさん割れてたから、もう自転車で遊べないんじゃないか、家もたくさん潰れてたから、友達の家に遊びに行ったりできないんじゃないかと思った。
【能登の小学校に戻って】
クラスメイトが能登を離れて転校していた。さよならも言えなかった。さみしかった。
【心に残っている支援は?】
自衛隊のお風呂(自衛隊の入浴支援)に行ったこと。自衛隊の人がお菓子をくれた。コンビニもやっていなくてお菓子もなかなか買えなかったからすごくおいしかったしうれしかった。だから自衛隊員になりたいとおもった。
最新番組ブログ
-

2026.01.30
あなたの危機一髪、ピンチだった話❣️来週は泉ピン子さん登場‼️
この日の朝6時、東京有楽町の気温は 1.5℃。 冷えます… 温かくしてこの冬を取り切りましょう! 春まであと少し・・・と思いたい・・・ ◾️先日1月28日我らの...
-

2026.01.23
教えて! あなたの何でもベスト3!
この日の朝6時、東京有楽町の気温は 1.1℃。寒!! ■今回の放送は… 『教えて! あなたの何でもベスト3!』 1月23日は「ワン・ツー・スリーの日」なんだそうです。...
-

2026.01.16
あなたのヒーロー・ヒロイン教えて🦸
この日の朝6時、東京有楽町の気温は 8.9℃ ほんのりあったかい朝☀️ ■今回の放送は… 『あなたのヒーロー・ヒロイン教えて』 皆様のあったかいメッセージあり...
-

2026.01.09
勉強の思い出・・・
この日の朝6時、東京有楽町は 3.2℃ 寒い… ◾️年末の一之輔サンタでスタジオ見学券が 当選した 千葉県八千代市にお住まいの 山中さんファミリーが ニッポ...
-

2026.01.02
2026年 今年もよろしくお願いいたします🙇♀️
2026年 初回は 1月2日(金)生放送です❤️ 朝6時 東京有楽町の気温は 4.5℃・・・🥶 ◾️番組のオープニングはニッポン放送前の交差点から! ◾️なぜ...