放送局・放送日時
- ニッポン放送
- 土曜日 22:00~22:30
- ABCラジオ
- 日曜日 12:30~13:00
- 南日本放送
- 日曜日 17:00~17:30


1月 30日(31日)の放送では、馬術の稲葉将(いなば・しょう)選手にリモートでお話を伺いました。

1995年生まれ、25歳の稲葉選手。
子どもの頃から野球が好きで、地元の野球チームに入っていましたが、学年が上がるにつれ体がついていけなったといいます。
先天性脳性まひによって両足にまひがあり、リハビリのため何か体を動かせるものがないかと探していたところ、母親が家から通える場所にある乗馬クラブの新聞記事を見つけます。
その乗馬クラブにはホースセラピーの活動をしている方がいて、もともと動物が好きだったことから一度行ってみようということで行ったのがきっかけとなりました。
そうして中学に上がる前の小学6年生のときに、乗馬を始めました。
本格的に馬術競技へと転向したのは、今から 3年半前の大学4年生のとき。
それまで「パラ馬術」のことは話に聞いて知っていましたが、「いつかやってみたい」と思うに留まっていたといいます。
そんな考えが変わったのが、東京2020大会の存在でした。
「やはり東京オリンピック・パラリンピックというのが競技を始める大きなきっかけでした。大学の時にオーストラリアに留学して、留学から帰ってきた時点で東京2020大会まで残り3年ちょっと。東京2020パラリンピックを目指すならギリギリ最後のタイミングかなと思って、今所属している静岡乗馬クラブに受け入れてもらえないかと話をしに行きました」
57歳でロンドン2012パラリンピックに出場した浅川信正(あさかわ・のぶまさ)さんのもとで本格的に馬術競技の指導を受けることになった稲葉選手。
競技を始めてわずか1年後の2018年には日本代表として世界選手権への出場を果たしました。
初めて大舞台となった世界選手権での経験をこう語ります。
「馬術競技を始めてまだ1年以内だったので、まずは出場することが目標でした。こんなに大きな大会にそれまで出たことがなかったので、実際に出場することができて、場の雰囲気や世界のトップ選手たちの演技を間近で見ることができてすごく良い経験になりました。しかしそれと同時に、僕はその時点では『出場する』だけでしたが、上を目指してやっているヨーロッパの選手たちは(世界選手権に)出るのは当たり前、そこはあくまでスタートラインで、そこからさらにどうしていくかということを考えているのを肌で実感しました。東京2020パラリンピックに向けて、自分もそうやっていかなければならないと思い、またひとつギアが上がるきっかけになりました」
競技を始めた当初からの目標を達成するため、馬術の本場・ヨーロッパでも合宿を行うなど練習を積み上げている稲葉選手。
ブラシがけをしたり一緒にいる時間を長くとったり、パートナーである愛馬とのコミュニケーションも欠かすことはありません。
馬術競技を始めたことで「自分に自信を持てるようになった」と笑顔で語ります。
応援してくれる方も増え、サポートしてくれる方からの声もダイレクトに届くようになるなど、周りの環境も変わっていきました。
「人と馬のコミュニケーションやコンビネーション。そして、馬の迫力やその優雅さが馬術競技の魅力」と話す稲葉選手。
次回は、昨年11月、東京2020大会で馬術競技の会場となる馬事公苑で開催された「第4回 全日本パラ馬術大会」での演技を振り返ります。
どうぞ、お楽しみに!
1月23日(24日)の放送では、前回に引き続き、ボートの有安諒平(ありやす・りょうへい)選手にリモートでお話を伺いました。
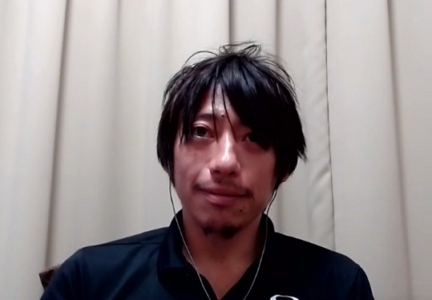
大学時代に視覚障がい者柔道を始め、強化指定選手にも選ばれた有安選手ですが、2017年、ボート競技へと転向しました。転向を決めた理由をこう語ります。
「大学卒業後、研究職の仕事に就き、そのあと大学院に進学して、日中は仕事、夕方から研究、それが終わってようやく競技活動という生活を送っていました。道場が開いている時間に(柔道の)稽古に行けず両立は難しいかもしれないと思い始めた頃、東京都と東京都障害者スポーツ協会が行っている『選手発掘プログラム』に参加する機会がありました。いろいろな競技団体の方が来ていて、そこでボート競技の方から『ローイングエルゴメーターという機械を使って夜でも自宅でトレーニングができるし、練習して体さえ作れば技術はあとからついてくる』という話を聞いて、やってみようかなと思いました」
転向後は育成選手を経て、2018年9月、ブルガリアで開催された世界選手権に日本代表として出場、PR 3男子ペアで4位入賞を果たします。
2019年からは日本ボート協会強化指定選手となり、同年10月に韓国で開催された2019アジア選手権ではPR3クラスで準優勝しました。
このアジア選手権での戦いは「悔しかった」と振り返ります。
「この大会が僕の出場した直近の国際大会となりますが、結果こそ“準優勝”ですが、今までずっとライバルでやってきた韓国チームとの対戦で、日本がずっとリードし続けていながら最後の最後で逆転されてしまったという試合でした。非常に悔しくて、今でもその悔しさがバネになって努力を続けることにつながっています。僕の中ではとても印象深い試合でした」
競技歴3年にして、日本代表として世界の舞台で戦う有安選手。
ボート競技では、新しい選手も絶賛募集中だということです。
「老若男女、子どもから大人まで誰でもできますし、僕もまったくの初心者の状態から始めました。大学や大人になってから始める方もたくさんいるので経験は関係ありません。視覚に障がいのある選手、肢体不自由の選手、そしてコックスは障がいがなくてもパラリンピックに興味があれば誰でも参加できるので、ぜひ興味のある方は日本ボート協会にアプローチしてください!」
ボート経験者の鈴木亮平さんからも「本当にボートは気持ちいいですよ」というお言葉。
「乗らないと経験できない感覚」、ぜひ体感してみてはいかがでしょうか。
東京2020パラリンピック出場を目指す有安選手は、現在、冬季パラリンピック競技のクロスカントリースキーにも取り組んでいます。
「クロスカントリーの動作とボートの動作はけっこう似ているところがあって、クロスカントリーの選手で夏場のトレーニングとしてボートをやっている選手がいたり、オリンピックのボート日本代表チームが冬場にクロスカントリースキーの合宿をしたこともあります。お互い競技特性が近い競技というところで、僕もトレーニングとして2年程前から取り組んでいました。そういう中で東京2020パラリンピックの先を見据えたときに、競技として取り組んでいきませんかということになり、今ガイドの選手と一緒にパートナーを組んで挑戦を始めました」
ボート競技同様、クロスカントリースキーにおいても大きな目標を掲げています。
「もちろん競技に取り組むうえでは、一番大きな目標としてパラリンピックがありますが、経験もまだまだ浅いですし、現実的にはさらに先ということになるかもしれません。けれども、もちろん来年の北京冬季大会も視野に入れながら活動しています!」
何足ものわらじを器用に履き、競技にも仕事にも全力で邁進する有安選手。
東京2020パラリンピックにかける思いを力強く語りました。
「東京2020大会が1年延期となり、選手たちはこの1年間、(東京2020大会で)最高のパフォーマンスを発揮できるように日々トレーニングをしてきました。日本全体が新型コロナウイルスによって元気のない状態が続いているので、そこで我々が活躍することで日本を元気にできればいいなと思っています。ぜひとも応援よろしくお願いいたします!」
最後に、上を目指して進もうとする方に伝えたい“Going Upな一言”を伺いました。
『挑戦と行動』
「常にいろいろなことに挑戦するのが好きで、何事にも挑戦していきたい」と語る有安選手。年齢を重ね、挑戦することに対して対価を得るには、必要な準備や環境調整といったいろいろなことをしなければ(その挑戦は)身にならないと感じるようになったといいます。やりたい、挑戦したいと思ったことに対してきっちり行動し、一つひとつ環境を整えながらその挑戦を成功につなげていく努力をしていく、そんな思いがこの言葉に込められています。
有安諒平選手のリクエスト曲:LOST IN PARADISE feat. AKLO / ALI
次回のゲストは、馬術の稲葉将選手です。
どうぞ、お楽しみに!
1月16日(17日)の放送には、ボートの有安諒平(ありやす・りょうへい)選手にリモートでご出演いただきました。
1987年2月生まれの33歳。
アメリカ・サンフランシスコで生まれ、5歳頃、日本に帰国したそうです。
視覚に障がいがある有安選手は、大学時代に視覚障がい者柔道を始め、強化選手として活躍。そして、2017年にボート競技へと転向しました。
転向後はボート日本代表として世界選手権やアジア選手権に出場するなど経験を重ね、現在、東京2020パラリンピック出場を目指しています。
ボートは2000mの距離を漕いで着順を競う競技。
カヌー競技と間違えられがちですが、ボートは進行方向に対して背を向け(選手の体の)後ろ向きに進むのに対し、カヌーは体が進行方向を向き前方向に進むので、体の向きが180度反対になります。
パラリンピックのボート競技は障がいの種類や程度により、PR1、PR2、PR3の3つのクラスに分かれており(※PRは、Para Rowing パラローイングの略)、クラスごとに出場できる種目が決められています。
PR1は1人乗りの種目(男女別)、PR2は2人乗り(男女1人ずつ)の種目、そして、有安選手が出場するPR3は4人の漕手(男女2人ずつ)と“コックス”と呼ばれる舵手が乗り込んで行う種目となります。
PR3は、視覚に障がいのある選手と肢体不自由の選手が対象で、漕手4人の障がいの組み合わせは基本的に自由です(視覚障がいの選手は2名まで)。
また、コックスは男女どちらでも可能で、障がいの有無を問わないため健常者も務めることができます。
有安選手は“視覚に障がいのある”、“男子選手”ということで「出力が期待される」ポジション。
「とにかくフィジカルを鍛えて、船(艇)を運ぶ役割として、エンジンとして働くことが求められている」といいます。
実は、鈴木亮平さんもボート競技経験者。
俳優の仕事を始めた頃、大学の漕艇部を舞台にしたドラマ「レガッタ~君といた永遠~」(2006年)に出演しました。
「撮影がすごく楽しくて思い出に残っている」と話す鈴木さんですが、とにかく朝が早く、午前4時に起きてみんなで艇庫から出て行き、ボートを漕いでいたそうです。
有安選手によると、「日影が全くないところで行う競技なので、夏場は早朝と夕方に練習することが多い」のだそうです。
撮影中に鈴木さんが気付いたのが「(ボートの選手は)上半身をすごく使っているように見えけど、意外と脚がムキムキ」だということ。
ボートのシートはスライド式になっていて前後に動き、脚を伸ばしてオールを引いて漕ぎます。(※パラリンピックのボート競技ではPR3クラスのみスライド式シートを使用します)
「人間の体は脚の方が筋肉が大きいので、体幹や脚といった大きな筋肉を使って出力を伝えます。腕を使っているように見えて、実は腕よりも下半身、体幹を使っています」と有安選手が教えてくれました。
さらには、上半身にも繋がりがあるので“デッドリフト”(ウエイトトレーニングの一種)の動きが一番近いといい、「2000mの距離を大体200回から250回くらいで漕ぎ切るので、全力で200回デッドリフトをやるような競技ですね」と笑みを浮かべながら話しました。
スタートからゴールまでの2000m。
全員で淡々と同じ動作を繰り返しているように見えますが、クルーの間では様々なドラマが繰り広げられているといいます。
「僕はクルーボートの一番前で漕ぐポジションで、漕手は僕の背中を見ながら後ろに三人並んでいます。例えば1000mくらいのところで僕の後ろの選手がだんだん苦しくなってリズムが崩れて来ると、僕は『このリズムを崩さないんだぞ』と背中で伝えます。さらに後ろの選手が1500mの一番つらいところで苦しくなってどんどん崩れてくると『前のふたりで支えるぞ』と意識を持ってふたりで前へ運んで行きます。そしてゴール直前、ラストスパートをしなければいけないところで僕が苦しくなってリズムが上がらないとなれば、後ろの3人ががんばってピッチを上げ、そこに僕も乗っかって四人全員で最後まで漕ぎ切る…無言ではありますが2000mの間にいろいろな会話をしています。そんなドラマを見ている方にも楽しんでもらえると思います」
ひたすら同じメンバーでずっと動作を繰り返して練習しているからこそ、メンバーの調子が悪かったり、重心のリズム感が揃っていなかったりすると、すぐに気付くそうです。
一方で、四人のリズムが揃った時は、船がスーッと滑るようにスピードが出ると話します。
力と呼吸、そして心を合わせ、2000m先のゴールに向かって進んでゆくボート競技。
次回は、有安選手とボート競技の出会いについて伺います。
どうぞ、お楽しみに!