【大人のMusic Calendar】
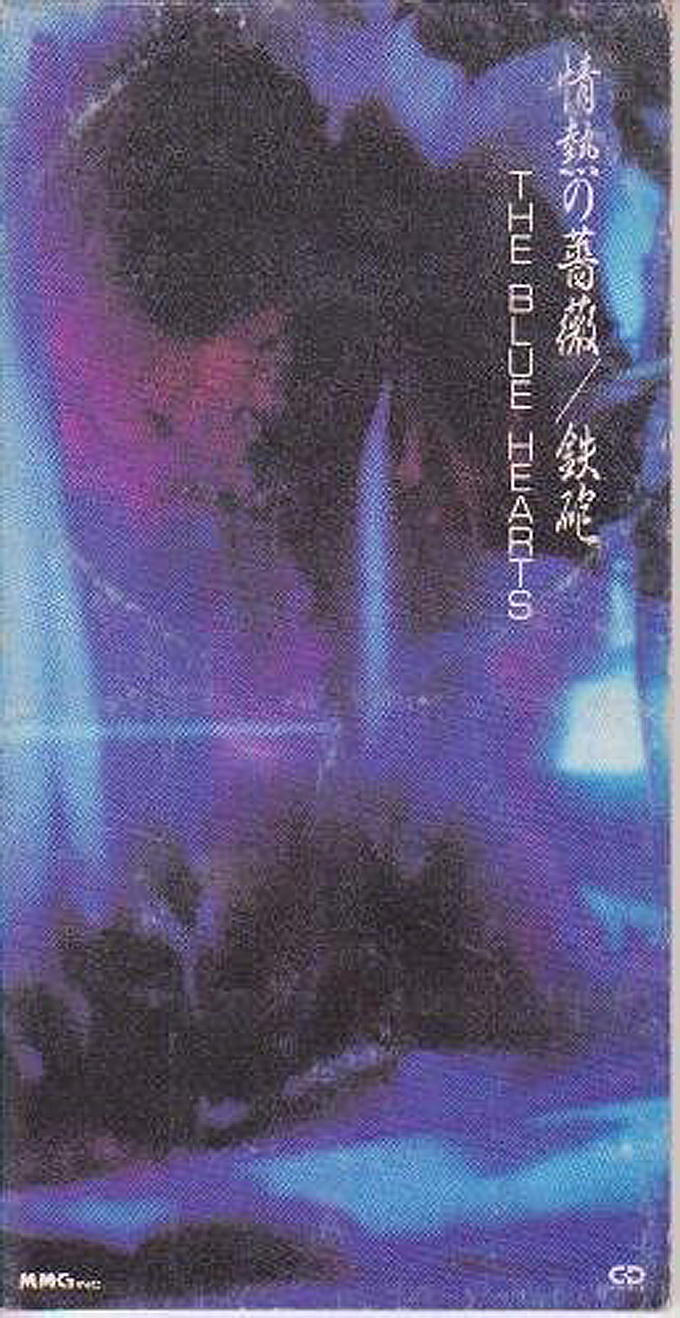
1990年8月6日はザ・ブルーハーツのシングル「情熱の薔薇」がオリコン1位を獲得した日だ。この曲はTBS系ドラマ『はいすくーる落書2』の主題歌となり、50万枚を超える大ヒットを記録した。88年リリースの「TRAIN-TRAIN」も『はいすくーる落書』主題歌だったので、その流れでのタイアップだろう。パンクバンドが日本のシングル・チャートのトップに立ったのは彼らが初だ。つまり8月6日はパンクがお茶の間に届いたことを象徴する日ということになる。それもちゃぶ台返しのないお茶の間だ。ザ・ブルーハーツ登場以前のパンクロックの一般的なイメージは破壊的、攻撃的、反抗的、暴力的といったものだった。が、彼らの奏でるパンクは強面なイメージとは一線を画した、人懐こくて、自由な音楽だった。彼らの音楽は中高生はもちろん、老若男女、幅広い層から支持された。口ずさみたくなったり、楽器を弾いたこともないのにバンドを組みたくなったり、わけもなく叫びたくなったりする。彼らの音楽は日々の生活を揺さぶるエネルギーを有していた。
ザ・ブルーハーツは甲本ヒロト(ボーカル、ブルースハープ、ギター)、真島昌利(ギター、ボーカル)、河口純之助(ベース)、梶原徹也(ドラム)の4人によって1985年に東京で結成されて、1987年にメジャーデビューしたバンドである。筆者が彼らのライブを初めて見たのは86年3月に渋谷東映映画館で行われたイベント、アトミックカフェでのステージだった。有頂天、ゼルダ、スタークラブなど、すでに独自の地位を築いていた他の出演バンドと違って、彼らはまだ無名だったのだが、彼らの演奏の衝撃は大きかった。彼らが登場したのは午前3、4時ごろで、寝ている人もたくさんいた。ヒロトは「おーい、みんなー、起きてくれー、聴いてくれー」と言いながら手をばたつかせると、おもむろにジーンズを脱ぎ、全裸になったのだった。その瞬間、熟睡していた観客が起きて、ステージに釘付けになったのは言うまでもない。彼らの奏でる音楽もまさに全裸そのものだった。装飾も誇張も隠蔽もない。むきだしの思いが真っ直ぐ届いてきた。
ロックンロールやパンクが“発明”であるのと同じように、ザ・ブルーハーツも“発明”だった。シンプルな言葉を明瞭な発声で歌うボーカル、自分も弾けそうだと思わせるストレートなバンドサウンド。歌詞も画期的だった。攻撃するパンクではなくて、攻撃される側、弱者の側に立ったパンク。「ドブネズミみたいに美しくなりたい」と歌われる「リンダリンダ」、パンクロックを「優しいから好きだ」と表現する「パンクロック」、「ガンバレ」と真正面から真っ直ぐに応援する「人にやさしく」。どれもパンクの掟破りみたいな内容の歌ばかりだ。だがその常識に縛られないところにこそ、ザ・ブルーハーツというバンドの独創性がある。音楽的にはポップでキャッチー。その根底には反骨精神もあるが、同時に繊細で純粋で無邪気。シニカルでシュールでコミカルな要素もある。シンプルなのに深遠で一筋縄ではいかない。戦略や計算とは無縁なところで自分たちの好きなロックンロールを追求するメンバーの姿勢も清々しかった。
彼らのデビューと前後して、日本の音楽シーンは空前のバンド・ブームを向かえていた。BOΦWY、HOUND DOG、レベッカ、BARBEE BOYS、TM NETWORK、米米CLUB、プリンセス・プリンセス、ユニコーン、JUN SKY WALKER(S)、THE BOOMなどが登場して、人気を博した。ホコ天が注目され、89年には『三宅裕司のいかすバンド天国』の放映もスタートした。ザ・ブルーハーツが結果的にバンド・ブームを牽引したバンドのひとつであることは間違いないだろう。だが、彼らは自分たちのペースで独自の活動を展開していた。彼らが急速に認知されたこと、バンド・ブーム、ドラマのタイアップなど、ヒットの要因がたくさん重なる中でリリースされたのが「情熱の薔薇」である。純粋に曲としても優れていて、ポップなメロディを持ったエイトビートのロックンロールであり、多くのリスナーが彼らの音楽に求めるであろう要素を満たしていた。でありながら、この「情熱の薔薇」はいわゆるヒットソングとは真逆のベクトルを感じさせる不思議な曲でもあったのだ。
まず、大ヒットした曲なのに、サビが1か所しかない。1コーラス目はサビが登場せずに終わり、2コーラス目のABのあとに、タイトルネームを含む、あの有名なサビがやっと出てくるのだが、時間にして10秒たらず。こんなにも短いサビがたった1回しか出てこない曲はそうはないだろう。しかもその曲が50万枚を超える大ヒットを記録しているところがなんとも痛快だ。
もうひとつ、歌詞の内容がとても深遠だ。「情熱の薔薇」という曲名やサビや勢いあふれる曲調から、ポジティブな曲という印象を持っている人もたくさんいると思うのだが、実はかなりヒネリが効いている。最初のAメロの“時の流れは続くのか”というフレーズからして意味深だ。バンドブームの真っ直中であり、社会的にはバブル絶頂期に、すでにそうした状況の終焉を予測するかのような冷徹さがある。バンドがいつまでも続くとは限らないということを示唆しているとも取れなくはない。いきなり出だしで、永遠という概念への懐疑が歌われているのだ。2つ目のAの “いままで覚えてきたこと全部がでたらめならば面白い”という内容の歌詞も、この曲が学校を舞台にしたドラマの主題歌であることを考えると、かなりシニカルだ。学問の全否定、とまでは言わないが、知識や常識を疑う姿勢を感じとることができる。
2コーラス目のAメロの歌詞も深い。なるべく小さな幸せとなるべく小さな不幸せを集めようと歌われていて、やや難解だ。かつてヒロトにインタビューした時に、幸福という概念について、「相対的なものなのではないかと思う」と答えていたのが印象的だった。例えば、水の中でおぼれそうになって、助かった時には、呼吸できることをなんて幸せなんだろうと感じるわけで、幸福と不幸とは状況の落差の感じ方によって決まるのではないかと、彼は語っていたのだ。この歌では落差の少ない日々、さりげない日常のかけがえのなさを歌っていると解釈できなくもない。2010年代後半の現在、そうしたテーマの歌はたくさんあるが、90年にそうしたテーマを内包した歌を歌っていたところからは彼の先見性を強く感じた。この曲の中で甲本ヒロトは“永遠とは?”“幸福とは?”という人間としての根源的な問いかけをしている。
ザ・ブルーハーツは甲本ヒロト、真島昌利という2人の類い希なソングライターが在籍していたという点でも突出していた。個人的には勝手に“詩人のマーシー”、“野人のヒロト”という分け方をしていたのだが、「情熱の薔薇」の哲学的な歌詞から判断すると、ヒロトは“野人”ではなくて、“超人”という言い方がふさわしいかもしれない。このふたりは現在、ザ・クロマニヨンズとして活動しているが、ザ・ブルーハーツからの継続性はまったくない。過去を振り返らず、今の瞬間を生きる、その姿勢そのものもまさにロックンロールだ。
ザ・ブルーハーツは音楽シーンに大きな影響を与え、多くのフォロワーを産み、1995年に解散した。この解散はまるで、「情熱の薔薇」の“時の流れは続くのか”という問いに対する答えのようでもあった。その後、彼らの残した名曲の数々は、多くのミュージシャンによってカバーされ、またライブでも歌われている。が、ザ・ブルーハーツが再結成して、ザ・ブルーハーツの曲を演奏することはおそらくあり得ないだろう。その潔さ、儚さ、せつなさも彼らの音楽に唯一無二の輝きを与えている。もしも永遠があるとするならば、それは形がなくなってしまった後から出現するものだろう。
【著者】長谷川誠(はせがわ・まこと):1957年北海道・札幌生まれ。小学生の頃に壁新聞に夢中になり、文章を書く人間になりたいと思ったのがこの世界に進むきっかけ。出版社勤務を経て、フリーランスのライター、音楽評論家に。吉川晃司、奥田民生、TRICERATOPSなどのアーティスト関連書籍の構成を多数担当。著書『WITH THEE MICHELLE GUN ELEPHANT』(ぴあ)、『 PRINCESS PRINCESS DIAMONDS』( シンコーミュージック)など。





